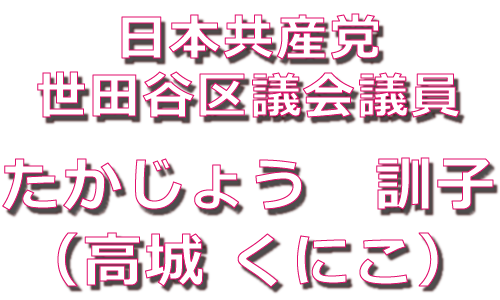

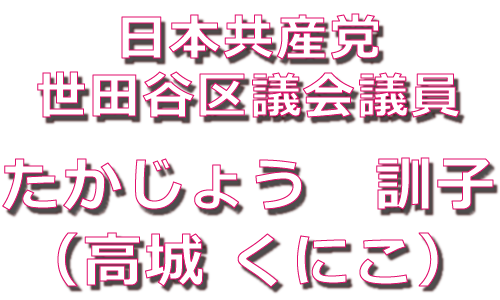

たかじょう訓子の新しいリーフレットができました。
シングルマザーとして苦しい日々の中で子育てを続け、今、成長した娘と息子に感謝しながら議員活動をしています。
そして、苦しいのは私のようなひとり親だけではなく、経済的なことで学ぶことが困難な学生、爪に火を燈すように生活する高齢者など、この国の悪政に心を痛めている人たちがなんと多いことかと実感しています。
「子どもの貧困対策」は私のライフワークです。議員一期目から世田谷区議会でこの分野で要求してきたことが次々と成果になっています。
誰もがくらしに希望が持てる政治の実現のために力を尽くす決意です。3期目も引き続き、区政で奮闘してまいります。
1965年栃木市生まれ。
県立栃木女子高校卒。建築設計事務所に勤務。
新日本婦人の会で子ども・女性の地位向上の活動に従事。
2015年世田谷区議会議員に初当選、現在3期目。南烏山2丁目在住。

令和7年 第2回定例会 一般質問
10月からの飲食料品の値上げが3000品目を超えるなど、物価高騰に歯止めがかかりません。7月の参議院選挙では、日本共産党をはじめ各党が消費税減税、賃上げや、社会保険料の引き下げを公約に掲げました。国での推進とともに、区民生活を守るための世田谷区での取り組みが必要です。区議団は公契約条例(区が発注する契約について労働者の賃金条件などを定めた条例)の労働報酬下限額引き上げ、国民健康保険料の負担軽減を9月の第3回定例区議会で求めました。
2025年度の全国平均の最低賃金が1,121円となりました。しかし、区民生活を守る賃上げには、1,500円を超える更なる底上げが求められます。代表質問で賃金の底上げに対する認識と、国に対して最低賃金の引き上げを求めました。
保坂展人区長は「区は、公契約条例に基づき…区独自の労働報酬下限額を今年度は1,460円と最低賃金を上回る下限額として設定をしてきた…労働報酬下限額の引き上げを広く最低賃金をめぐる議論の中で発信し、世論に訴えることによって、民間の賃上げを後押しする」と答弁しました。
さらに区議団は、公契約条例の労働報酬下限額の引き上げを求めました。区は「様々な要素を総合的に勘案したうえで適切に決定していく」と答えました。
国民健康保険料の負担が区民生活に重くのしかかっています。日本共産党は、全国知事会の要望を踏まえ、1兆円の公費負担増を行うこと、均等割の廃止で国保料を引き下げることを提案しています。家族の人数に応じてかかる均等割は、子どもが多いとその分国保料が高くなり子育て支援に逆行します。
区議団は、均等割は18歳までゼロ円とし、国庫の負担割合を増やして国保料を引き下げることを、区長会を通じて国や都に要請を強めることを求めました。区は「国に粘り強く要望し続けるとともに…国民健康保険料の区民負担が急増しないよう、運営に努める」と答弁しました。
あらゆる差別と排外主義を許さない社会を
7月の参議院選挙において、政権与党が衆議院・参議院ともに過半数割れするという大きな変化が生まれた他方で、特定の外国人などに対し、排除または拒絶の姿勢を示す、極右・排外主義勢力の台頭という事態が生まれました。
日本共産党は、生活が苦しいのは外国人に原因があるのではなく、国民犠牲の政策をすすめている自民党政治にあり、この政治を変えていく展望を示すことが極右・排外主義を克服する最も根本的な道であると考えます。政治の転換と極右・排外主義とのたたかいを断固としてすすめる役割を発揮して奮闘します。9月の区議会では他会派からも差別や排外主義を批判する多様な議論がありました。
区長は「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例の本旨に則り、差別や排外主義を固く禁じるという立場を鮮明にしながら、全ての人が安心して暮らせる地域社会の実現をはかっていく」と答えました。
大雨による浸水被害を起こさない根本的な対策を
9月11日午後、世田谷区で猛烈な雨が降り、深刻な浸水被害がおきました。
区議団は、浸水被害を受けた尾山台三丁目、奥沢七丁目の店舗等に状況と要望の聞き取りを行いました。
議会質問の中で、園庭や室内に水が入り込み、子どもたちを2階に避難させた保育園や、店内に水が入り込んで製氷機が駄目になってしまった飲食店などの実態を取り上げました。気候変動のもとで大雨の発生頻度も強さも増加している中で地域住民、事業者の方は度重なる浸水被害で、何とかしてほしいとの思いをますます強くしています。止水板設置助成とともに、浸水被害そのものを起こさない根本的な対策を求めました。
区は「グリーンインフラの考え方も踏まえた流域対策の推進は元より、下水道の増強施設の早期整備の実現に向け(都に)要望するとともに…下水道局と連携・協力し激甚化・頻発化する豪雨への対策強化に努める」と答弁しました。
記録的猛暑!
小中学校の暑熱対策が進んでいます
区議団は夏休み中の塚戸小を視察し、断熱対策の効果を体感しました。
塚戸小では最上階の天井裏断熱や二重サッシなどの効果を、年間を通して調べる実証実験を行っています。東大の前真之(まえまさゆき)研究室が行なっている「学校断熱改修推進プロジェクト」の一環で、北海道から九州までの気候特性の異なる全国6か所の学校で行われています。
近年の猛暑で教室のエアコンが効かないことが問題となっています。古いエアコンの更新とともに断熱化を求めてきました。今年度は41校でエアコン更新や断熱・暑熱対策を
8月までに完了したことを確認しました。対策が完了していない23校の対応を急ぐよう求めると、区は来年7月までに最上階天井裏の断熱材設置、屋上断熱塗装、遮熱カーテンなどの対策をとると表明し、昨年までに対応済みの学校と合わせ、全校が来年夏までに何らかの対応をすることが確認できました。
東京の住宅価格が高騰し家賃に波及。家が持てない、住めないという深刻な事態が広がっています。「住まいは人権」であり、憲法25 条が保障する生存権の土台です。世田谷区が安心して暮らせる住まいの提供に力を尽くすことは、区民に果たすべき責任です。
物価高で家計が苦しい上に、毎月の高すぎる家賃が重くのしかかり、もう世田谷区に住み続けられないと区外へ転出せざるをえない方がいる中、区議団は6 月の区議会質問で、区営住宅を増やす方針を持ち、若者・現役世代が低廉で安心して住み続けられる住宅整備を区としてすすめることを求めました。区は「都営住宅の建替えや、区への移管、将来の区営住宅の建替えなどの機会を捉えて、若者・現役世代を含めた、低廉で安心して住み続けられる住宅の整備に向けた検討を進めていく」と答弁。
続く9月区議会でも、この問題を取り上げ、昨年の区営住宅の応募倍率は14倍。抜本的な拡充を求めました。区長は「世田谷区としての公共住宅資源の拡充ということも課題として検討していきたい」と答えました。
ふるさと納税124億円流出(令和7年度)
官製通販 高額納税者ほど得をするしくみ
世田谷区におけるふるさと納税による財源流出額は、制度開始から累計で約691億円。庁舎の建て替え費用を大きく上回り、将来的な行政サービス低下が危惧されるほどです。
地方税は、自治体の行政サービスの費用を住民が負担し合う仕組みです。ふるさと納税を利用すると、住んでいる自治体のサービスを受けるのに、そこには住民税を十分に払わないという事態がおきます。官製通販と批判される返礼品ありきの現状は、ふるさとやゆかりの自治体を寄附で応援するという制度本来の趣旨からもかけ離れています。
世田谷区では、 所得階層300万円以下の方のふるさと納税額は平均で3万円程度。4千万円超の方は約180万円(被災地への寄付など、返礼品のない寄付も含む)。大金持ちほど多くの返礼品をもらえるため得をする仕組みです。
地方の財源として使えるはずの収入が、大金持ちへの返礼品や大手ポータルサイトへの手数料となります(世田谷区の、ポータルサイトへの支出は約3300万円)。
日本共産党は、返礼品競争の過熱防止や、富裕層優遇とならないよう、廃止を含めた抜本的な見直しを求めています。
一律2千円の自己負担で納税額の3割
の返礼品がもらえる
▶納税額3万円の場合:9,000円分
▶納税額180万円の場合:540,000円分
生理用品の区施設への設置実現
200カ所程度を想定(来年度から)
学校を始めとした公共施設への生理用品の設置を区議会でたびたび求めてきました。小中学校のトイレへの設置は全学校で実現し、来年度から、区内200カ所程度の施設に生理用品が設置されることになりました。
区は、「生理によるジェンダーギャップを少しでも解消し、生理に対する無理解や偏見を無くすとともに、共に支えあう社会の実現のため、生理用品を区施設に設置する」とし、併せて女性相談窓口を案内するカードを設置し、相談(DVなど)につながりやすい環境も整備していきます。
老後の介護や医療、亡くなった時の葬儀や遺品整理、相続など、不安を抱いている身寄りのない方がおられます。
この間区議会質問でも取り上げてきましたが、ようやく世田谷区でも、区民の「終活」を支援し、個人の尊厳が守られ、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のため、(仮称)終活支援センターを開設する検討が始まりました。(令和8年7月開設予定)
頼れる身寄りがなく、十分な資力が無い高齢者に対し、低廉な利用料でサービスを行います。
● 定期訪問サービス
● 金銭管理手続き支援
● 入院入所手続き支援
● 賃貸物件契約・更新時の緊急連絡先対応
● 火葬・納骨支援
● 死後の賃貸物件対応
東京都と都内区市町村は、概ね10年毎に優先的に整備する都市計画道路(幹線道路や補助幹線道路)を選定し、必要性の検証も行ってきました。
計画の大部分は80 年前に作られた戦災復興道路計画で、現道のない住宅地や商店街を貫く計画です。必要性の検証と言っても、文化財、商店街、公園、緑地、コミュニティなどへの影響の検討は行ってきませんでした。
現計画の期間は今年度末で、現在改定作業が進められています。住民とともに、廃止を含めた見直しを検討するよう求めました。
東京都ベビーシッター利用支援事業は、ベビーシッター利用料について、区市町村が負担軽減を行う場合、その費用の一部を都が補助するものです。
ベビーシッターの利用ニーズがあること、世田谷区の既存保育サービスが需要を満たしていないこと、さらに、事業を行っている他区の区民と比べ、不利益となっていることも事実です。
しかし、東京都のこの事業におけるベビーシッターの研修方法や、事業者任せの保育実習の仕組み、保護者同意があれば研修を終了していないベビーシッターを派遣できることなど、現時点で、保育の質を重視している世田谷区として、密室性や第三者による保育の質の確認に関する懸念、保育の質の担保に課題があり、この仕組みを導入することに大きな不安があることから、反対しました。
今年は戦後80年、被爆80年、世田谷平和都市宣言40周年、世田谷平和資料館(せたがや未来の平和館)10周年の節目の年。そして昨年の日本被団協へのノーベル平和賞を受けて、今こそ核兵器のない世界を実現させるために、世田谷からも声を上げていこうと、平和団体のみなさんからの要望を受け、世田谷区議会からの意見書を提案しました。
坂本みえこ区議が提案理由を説明し、続けて、この意見書の内容が不十分だから、という理由で公明党が反対討論。生活者ネットワークの関口江利子議員が、被爆2世として「核兵器の恐ろしさを知ってください。
核兵器は核抑止という都合の良い言葉で、手綱が握れるような代物では無いことを知ってください。」と賛成討論を行いました。
どの党が核兵器のない世界の実現に向けて前向きなのかが、よくわかる結果となりました。
福祉保健常任委員会で趣旨採択となりましたが、本会議において賛成23、反対26で不採択となりました。
11月11日、区は都市整備常任委員会において、区内のバス路線の廃止・減便の危機を迎えていることから、コミュニティ交通へ行政支援を行うことによって路線を維持していく考えを明らかにしました。今年4月から住民の皆さんともに区へ求めてきた「くるりんバス」減便対策が一歩前進しました。
「くるりんバス」は、小田急バス株式会社により運行される、祖師ヶ谷大蔵駅~ウルトラマン商店街~成城学園前駅(砧支所)を循環するバスです。
この4月に、くるりんバスの時刻表が改定され、便数が半減しました。朝7時台が4便から2便へ、10時11時、15時16時台の便が無くなり、夜も19時台で終わってしまいます。
住民の方から、「通院の際、帰りのバスを12時まで待たなければならない」「買い物時間のピークの15時16時にバスがないのは困る。」住民、地元商店からも「元に戻してほしい」との切実な声が寄せられています。
7月16日、地域住民の方が『くるりんバス』の減便を元に戻して欲しいと、816筆の署名を保坂区長宛に届けました。私も同席しました。
大平区長室長が対応し、『くるりんバス』は、住民との協働で作った路線であり、今後何ができるか所管と共に検討すると答えました。
9月11日、私は、路線バスの廃止・減便対策について国交省のレクチャーに、山添拓参議院議員、くるりんバスの減便を元に戻して欲しいとの運動をしてこられた住民の方5人と共に参加しました。
国交省の担当者からは、減便・廃止の状況や、バス運転手の賃金引き上げや待遇の改善、路線維持への補助、地方自治体の施策への支援などの対策等の説明がありました。
バス路線の廃止が2023年度、全国で2496キロメートル、都内では181キロメートルだったと説明があり、利用者減のほか運転手不足が大きな要因で、深刻化している減便・廃止の対策が喫緊の課題との認識が述べられました。
住民の皆さんからは、「地域を巡回するバスが4月から減便となり、高齢者が病院に行く時間帯の運行がなくなった」などと実情を説明し、現役のバス労働者からは「低賃金、長時間労働」など過酷な実情が語られました。
私からは、課題解消のため、事業者への直接支援の予算を思い切ってふやすことを求めました。
渋谷区、杉並区、練馬区、足立区などで行なっているコミュニティバスへの支援を、世田谷区では現状実施していません。
私は、第2回定例会第3回定例会と続けて『くるりんバス』の減便問題を取り上げ、区独自に運転手確保策として、家賃支援など、バス事業者への支援を行うよう求めました。
11月11日都市整備常任委員会において、民間バス事業者へのアンケート結果を踏まえ民間路線バス事業者への行政支援の方向性が以下の通り示されました。
①運行経費補助(減便阻止)
②事業継続維持費(担い手確保)
③バス運転士魅力アップ(バス運転士魅力アップ)
コミュニティ交通へ、区独自に行政支援を行うことによって路線を維持していく、コミュニティバス以外の路線については、東京都に対し支援を求めていくと答弁しました。
住民の皆さんが取り組んだ816筆の署名が区を動かしました。しかし、まだ、くるりんバスの増便には至っていません。区民の生活の足となる公共交通を確保する役割をひき続き区等に働きかけていきましょう。
第3回定例会 令和6年度決算特別委員会報告
どうなる?!千歳烏山駅前広場南側地区の再開発
千歳烏山駅前広場南側地区市街地再開発
駅周辺のまちづくりは住民参加で