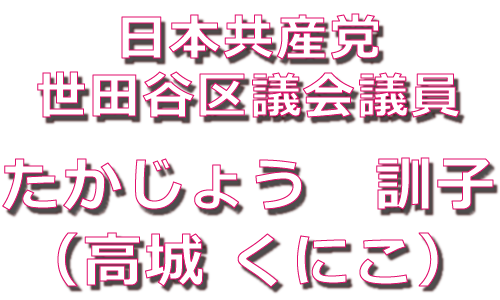

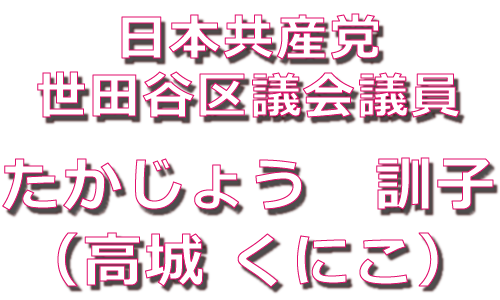

2024/10/10
日本共産党世田谷区議団の質疑を始めます。
まず、教員の働き方について伺います。
担任が配置できない、産休代替の先生が見つからないなど、教員の不足は深刻です。教員が足りない学校では、一人の教員が二クラスの授業を同時に進めるとか、授業に入る教員が毎時変わるために児童が不安定になるなど、子どもたちに大きなダメージを与えています。教員たちは、未配置の教員の分の仕事を負担するために、ますます疲弊していきます。教員を学校に配置するという最低限の教育条件整備が崩壊した重大な事態だと考えます。
しかも、教員不足の解決のめどが立ちません。教員からは、学校が回らなくなるのは時間の問題、このままでは学校が崩壊するという強い危機感が表明されており、その打開のために、教員の働き方の改善は喫緊の課題です。
日本共産党は、教員の働き方を抜本的に改善するためには、教職員の定数の抜本増、そして残業代の支給制度の確立、これは公立教員には残業代を支給しない制度、公立教員給与特例法、いわゆる給特法と呼ばれるものですけれども、定額働かせ放題と批判されているとおり、長時間労働の温床です。教育労働の特性に考慮した残業代の支給の法制度にかえて、残業代を支給することが重要だと考えています。
また、学習指導要領の改訂で過密なカリキュラムを緩和する。今の授業時数は、子どもに多過ぎて効率も上がりません。過密な学習指導要領を改訂し、子どもに合ったものにし、以前のように週一日は半日授業として、教員が授業準備など時間を確保できるようにすること、その際の子どもの居場所を公的に保障することなどを提案しているところです。
また、緊急の対策としては、多過ぎる業務量の断捨離の決断をすること、不要不急の業務の一旦停止、削減すること。世田谷区で言いましたら、学力テストや教科「日本語」など業務を一旦中止すること。また、初任者研修、年次研修を半分以下にする。教職員評価制度を中止する。部活動顧問の強要をなくし、土日の試合を減らすなどが必要ではないかというふうに考えています。
区は昨年、教員に対して働き方に関するアンケートを行いました。結果を拝見しましたが、本当にリアルな声が自由意見のところに表れていたというふうに思います。代替が見つからないなどで欠員を抱えている学校が多く、どこの学校も疲弊している。教員が授業や生徒対応といった本来すべきことに注力できる環境にしてほしい。私費会計の処理が非常に負担の大きい状態であるのに、担当の授業軽減等が設定されていない。会議も含む持ち授業数の上限を減らすか、規模の縮小をしてほしい。とにかく授業時数が多過ぎて、研究や能力開発に身が入らず、生産性が下がっている。授業を担える人材の採用や授業軽減時数の削減を検討していくべきだ、そういうふうに書いてあります。特に教科「日本語」は、国語と重なる部分も多く、一教科分多く教材研究、授業準備が必要になるから必要とは感じない、こんな声が上がっていました。
教員を増やすこと、教員の本来の仕事をするための事務や会議、研修や授業時数などの改善等が上がっているということです。今般、働き方改革の基本的な考え方が出ていますけれども、その中では、小学校高学年における教科担任制を導入する。そしてまた、区独自に教員の採用も行う。部活体制としては、部活動の地域移行、地域連携を行うこと、教員の事務負担軽減、学校施設と地域開放の業務に係る事務を委託する。学校と地域を結ぶコーディネーターなど、現在の地域や学校の状況に合わせて、改廃する、改めて構築する。教員のメンタルヘルス対策など、学校への支援の強化を行うということなどが示されています。特に区独自に教員を増やす方向性、これは本当に多くの方から寄せられている声ですし、ぜひこれは実現していただきたいです。
しかし、教科担任制導入を働き方改革の手法として導入する考え方には違和感を覚えています。教科担任制の是非については、教育効果や、そして子どもたちへの影響などを議論される中で導入すべきものではないかというふうに思います。
ここでお聞きしますけれども、教科担任制の教育的効果をどのように考えているのか伺います。
今回お示しした学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(骨子案)は、文字どおり教育の質を高めるためのものであり、教科担任制の導入もその一環となります。教科担任制の導入により、一人の教師が担当する教科数の減少や空き時間の増加に伴って時間的余裕が生まれ、教材研究が充実するとともに、複数回同じ授業を実施することによる授業改善も図られ、授業の質が向上すると考えています。
また、中学校は教科担任制であるため、子どもたちが中学に進学した際、学習や生活に順応しやすくなり、小中学校間の円滑な接続に寄与すると考えております。
私どもも、現場の教員の方にお話を聞くことがあるんですけれども、小学校では学習とともに養育面、特に小学校では養育面でのケアも重要な仕事だというふうに伺っています。ある学校で緊急対応として、図らずも教科担任制に近い対応を行わざるを得ない、そういう状況があったそうです。
そこで、教科担任制に近い状況が続いたんですけれども、そのときに、不登校児童が増えるという状況が生まれたと伺っています。子どもたちから見た効果、学習面だけではなくてメンタルへの影響、例えば担任との関係がつくりにくくなるのではないか。それから、担任が子どもたちと接する時間が少なくて、子どもに起こっている問題に気づきにくくなるのではないか。そういったことが懸念されるのではないかというふうに伺っているんですね。この辺はどういうふうに考えておられるのか伺います。
まず前提として、教科担任制は児童の発達段階を考慮し、小学校高学年での導入を想定しております。現在、世田谷区では、教科担任制導入に向けた東京都の指定研究を二校で取り組んでおります。生活指導面として、児童に多くの教師が関わることにより、多面的な指導、支援が可能になり、児童や学級の複雑な課題に対して、学年全体で組織的に対応できるようになったと聞いております。
生活指導でも、教員同士が情報共有し、複数の教師で児童の様子を見守ることで、様子の変化に気づくことができるとともに、児童からは学級担任以外にも悩みなどを相談しやすくなるなど、いじめや生活指導上の問題、養育面の課題についても、未然防止、早期発見につながると考えております。
また、学年担任が替わる場面、異動などで担当教科が変わるということもあると思うんです。小学校の教員のスキルの向上、これは全ての教科を教えられるという状況に今なっているわけですよね。スキルの向上の面から不安の声もあるんですけれども、ここについてはどういうふうに考えておられるんでしょうか。
小学校の教員は全教科を教えることが求められ、各教科の特性もあることから、ずっと同じ教科を担当するのではなく、一定期間で担当教科を変更するなど、教師の育成面も考慮することが望ましいと考えます。しかし、一つの教科を深く追求することで、全ての教科指導に共通する授業力である子どもの学びをファシリテートする力をより伸ばすことも可能です。長期的な視点で、学級担任として幅広い教科指導力を身につけられるよう配慮することが大切だと考えております。
もちろん、そういったことに気をつけていただきたいということもあるんですけれども、モデル校での経験、これはしっかりと研究していただきたいですし、先ほど述べました子どものメンタルがどうなのかとか、教員との関係が――教員というか、担任との関係がどうなのかとか、そういったことも含め、検証していただきたいというふうに思っています。
今回、教員を増やす仕掛けといいますか、東京都からのこれから始まるということで、これで教員が増やせるというのは、そういった仕組みになっているということもありますので、それはセットなんだろうというふうに思いますが、しっかりと検証していただきたいと。
それから、現場の先生の声というのがやっぱり重要だというふうに思いますので、しっかり今後、聞いていただきたいということを要望いたします。
次に、区立図書館の取組について伺います。
区民生活でも紹介しましたけれども、「世田谷から平和を考える――疎開児童と特攻隊員の出会い、そして特攻平和観音――学童疎開・特攻八十年」と題した資料パネル展や太子堂区民センターで行われた「鉛筆部隊と特攻隊」と題する下馬図書館主催の講演会など、この夏の区立下馬図書館での平和の取組は本当にすばらしいというふうに思いました。下馬図書館と平和資料館というのは、昨年度より平和について考える共同企画を実施しているとのことで、こうした取組を評価いたします。
下馬図書館は指定管理図書館です。今回の取組は、指定管理図書館になる前の直営の時代からあった話を指定管理館の職員がしっかり引き継いで、今回のような取組につながったというふうに伺っているんです。このように図書館の目的、機能を実現するためには、図書館員の役割が大変大きいというふうに思いました。
日本共産党は、区立図書館への指定管理制度には反対していますが、区立図書館全体の充実、このような取組をぜひ生かしていただきたいというふうに考えています。この間、区立図書館では、どのような取組をしてきたのか伺います。
委員御紹介の指定管理が運営する下馬図書館では、地域の商店街などと連携した世田谷公園での青空図書館や世田谷パブリックシアターと連携した大道芸イベントでのおはなし会や企画展示、昭和女子大学の学生と協働した子どもの絵本づくり講座など、様々な地域連携事業に取り組んでおります。
一方で、区職員が直接運営する図書館での取組の例示としましては、健常者が視覚障害者の方と交流しながら点字を知る点字で遊ぼうというイベントや、千歳船橋にゆかりのある森繁久彌氏の納涼森繁久彌映画会開催など事業企画を行っております。
本当にそういった取組がすばらしいなというふうに思います。地域の作家にちなんだ、今御紹介になったものもそうですけれども、地域の作家にちなんだ町歩きや平和の取組であるとか、歴史にちなんだイベント、災害対策や子どもの権利や包括的性教育、障害者理解など、社会問題を学ぶ機会を提供するイベントなど、各図書館の独自の取組を大いに進めていただきたいというふうに思います。
直営図書館や指定管理図書館がよい経験を交流して、区立図書館全体の質の向上、充実をさせていく必要があると思います。区の見解を伺います。
各図書館における取組は、館長会や担当者会などの場で共有しており、図書館同士で協力、共同して新たなイベントの実施などにつなげております。引き続き、各館の取組状況やノウハウの共有をすることで、図書館全体の質の向上、充実を図ってまいります。
それぞれの図書館のよい取組を区民に広く知らせることも重要ですけれども、効果的な周知を行えているかといえば、十分ではないのではないかというふうに思います。例えば、ホームページがとてもあっさりしているんですね。それぞれの図書館のカラーがあってもよいし、そのほかにもチラシ配布、さらなる区民の参加を増やす積極的な広報活動をしていただきたいなというふうに思っています。見解を伺います。
委員御指摘のとおり、このような取組は積極的に周知し、一人でも多くの利用者や区民に参加、体験していただくことが重要です。区報やホームページ、ポスター、チラシなどによる周知だけではなく、指定管理館ではデジタルサイネージを活用するほか、インスタグラムなどSNSによる広報活動に力を入れております。また、直営館である中央図書館においても、デジタルサイネージを活用し、区内で活動するブラックラムズの選手による手話に関する啓発動画を放映しております。今後は、他の地域図書館にも拡大導入する準備をしております。さらに、SNSの活用についても検討するなど、イベント情報の周知方法の拡大を図り、区立図書館全体のサービス向上充実に役立ててまいります。
会計年度任用職員の中には、司書資格をお持ちの方がおられるそうですけれども、司書資格のある職員が窓口と書架の整理などで忙殺されていて、司書のスキルが生かされていない、司書資格の有無も把握していないというふうに伺っているんですね。今後、区立図書館の司書資格のある職員の能力を生かして、区立図書館の質の向上に向けた積極的な取組を今後も期待いたしますので、どうぞ頑張っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
次に、砧図書館利用者懇談会について伺います。
区立図書館の中で唯一の利用者懇談会である砧図書館利用者懇談会が、このたび閉会したと伺いました。これまで月一回の例会には、図書館側から複数名参加してきました。二〇二四年三月の例会で、図書館側から利用者懇談会からの離脱を表明し、これをきっかけに図書館側が参加しないのなら懇談会の意味がないと閉会したとのことでした。利用者懇談会の中には、五十年以上続いた利用者懇談会がこのような形で閉会を迎えたこと、閉会の経緯について納得できずにいるメンバーが少なからずいると伺っています。
砧図書館は、昭和四十一年十一月一日に開架式で開設しました。文庫活動から始まり、住民の地域に図書館をとの要求の高まりから誕生し、間もなく六十周年を迎えます。砧図書館利用者懇談会は、砧図書館六十年の歴史の中で、五十二年間の長きにわたり地域で子どもと本に関わる活動をしてきた団体等と、図書館が意見交換を行う場となってきました。
司書の配置や本の増冊、団体貸出センターの設立など、要望に応え、区は砧図書館の充実を図ってきたと思います。ひいては地域住民の利益へとつながってきました。区内唯一の利用者懇談会です。五十二年も続いてきた砧図書館利用者懇談会が、図書館側からの会の離脱表明をきっかけに閉会したことは大変残念なことです。第二次世田谷区立図書館ビジョン第三期行動計画でも、地域で活動する団体との関係を築くとしており、参加と協働の区政運営を掲げる当区としても、このような対応はいかがなものかと言わざるを得ません。砧図書館の利用者懇談会の閉会は事実なのか伺います。
委員御指摘のとおり、閉会いたしましたのは事実でございます。利用者懇談会に出席する図書館の負担が高く、新たな図書館ビジョンの取組に注力したいという理由から、これからは参加できないと発言したことがきっかけとなったと聞いており、参加団体の皆さんで話し合っていただいた結果ではございますが、中央図書館長としましては残念に感じ、申し訳なく考えております。
区は、砧図書館利用者懇談会について、どう認識し、どう評価していたのか伺います。
砧図書館利用者懇談会は、これまで地域団体支援のため、個人貸出しとは別の団体貸出し制度の要望など、様々な御意見等を伺う区立図書館における唯一の懇談会でした。地域活動団体の皆様からの御意見などについてお伺いする場であり、これまで五十二年間、砧図書館の充実に貢献いただき、ありがたいと思っております。
今後、利用者からの要望があれば、復活することも検討していただきたいというふうに思います。さらに、各区立図書館の充実のために、全ての図書館に利用者懇談会を広げることを検討したらどうでしょうか、見解を伺います。
利用者懇談会につきましては、砧図書館での事例を他の地域館等で展開できるか否か、地域の声を見定めながら、地区の特性などにも考慮し、砧図書館も含めて検証してまいります。
砧図書館の利用者懇談会の方々と図書館との話し合う場をつくっていただくとか、話し合っていただきたいというふうに思っております。これは要望します。
次に、給食の質確保に向けた区の取組について伺います。
区は、食材費高騰への対応として、児童生徒の成長に十分な栄養やエネルギー量を考慮した給食を提供するために支援を行ってきました。食材費高騰の実情、現状、状況が給食の現場にどんな影響を与えているか伺います。
給食用食材の価格が上昇していく中で、各学校では発注前に価格を確認し、より安価な食材を選ぶ、調味料をまとめて購入し小分けにして使用するなど、食材費を抑えるための様々な工夫をしながら献立作成を行ってきました。区では、価格高騰に対応するため、令和六年度から給食費単価の一八%相当分を食材費に上乗せする食材費の増額を実施しております。
こうした経済状況に合わせた取組により、国の学校給食摂取基準に基づく児童生徒の成長に必要なエネルギー量や栄養素量を満たす水準を維持しながら安全でおいしい給食を提供しております。
現場でも大変な努力をしていただいて、大変ありがたいことだと思います。
物価高騰はすごく続いて、今でも続いていますけれども、この十月の値上げ品目は最多と報道されています。九月の消費者物価指数では、昨年の同じ月と比べてコシヒカリを除くうるち米が四二%、輸入の牛肉が一四・七%、トマトが一二・七%上昇しています。食材費の値上げに対する対応を、今後も機敏に行っていただきたいと思います。区の見解を伺います。
区では、これまでも食材価格高騰の状況に合わせて、食材費を増額するなどの対応を行っており、現在も毎月、食材価格の状況の確認を続けております。価格高騰がこのまま継続すると、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食水準の維持が難しくなることが懸念されます。
そこで、今後も引き続き食材価格の推移を注視するとともに、学校現場の栄養士等の意見も踏まえながら、給食を安定的に維持継続するために必要な食材費を確保できるよう、来年度に向けて給食費単価の改定を含めた検討を行ってまいります。
来年度予算での対応はもちろんのこと、現場の状況を把握していただき、必要であれば補正予算での対応を求めます。
それでは、質問者を交代いたします。