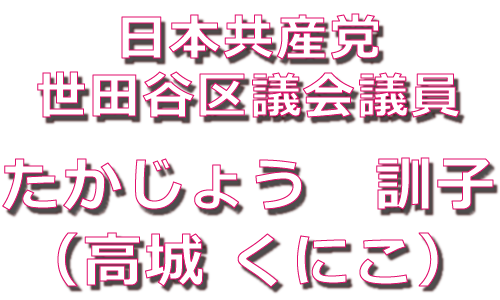

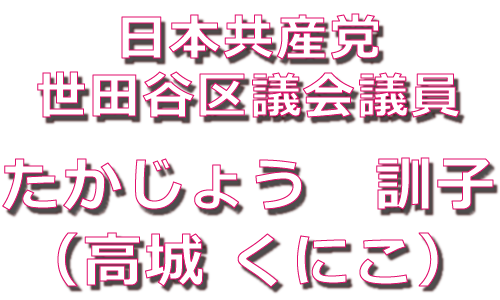

2024/10/09
おはようございます。日本共産党の質疑を始めます。
まず、次期事業化計画について伺います。道づくりプランなどです。
東京都と特別区と二十六市二町が共同で策定した東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)の期間が令和七年度末となります。これに合わせ道づくりプランの期間を二年間延伸しました。令和八年度からの次期事業化計画、道づくりプラン策定に向けた取組が始まるところです。今後、都市計画道路の路線ごとに必要性について検討し、必要と認められた路線のうち、優先的に進めるべき路線を優先整備路線として選定するというプロセスになろうかと思います。
これまで会派としては、区の根幹である参加と協働のまちづくりを進めるために、区民の多くの合意が得られない不要不急の都市計画道路は廃止を含め、見直すことを求めてきました。一方、都市整備方針素案の意見交換会、私、傍聴しましたけれども、子どもが病気になったときに家の前の道に救急車が入らなかったと、こうした狭い道の改善が必要との趣旨の発言がありました。今回の区民意識調査の結果でも、地域における日常生活での困り事の項目で二割半ばが道路が狭くて危険と回答しています。地先道路の整備こそ積極的に進めるべきというふうに考えております。
都内の都市計画道路の多くは、戦災復興道路として約八十年前に計画されたもので、各路線についてどのような必要性があるのかや、なぜそのような線形になったのかなどの記録はありません。地権者や周辺住民に相談したり、意見を聞いたりということも一切行われずに決められました。
都市計画道路整備方針で優先整備路線に選定されれば、住民にとっては数ある計画の中で、住まいがあるこの場所が優先的に整備する路線に決まり、立ち退きの対象になるということを、交渉の機会もなく突然知らされることになります。地域全体で必要性を感じていなければ、納得いくわけがありません。必要性の検討は大変重要ですし、住民にとってどうかという視点を区が持っていなければならないと思います。
この間、国の方針が変わり、全国での都市計画道路の見直しが進んできました。ところが、東京都はほぼ全ての都市計画道路については必要な路線だと固執し、世田谷区もこの間、必要性は認められていると都と同様の認識を示しています。
しかし、総務省では、日本の人口は二〇五〇年には九千五百十五万人となり、約三千三百万人減少すると推計しています。整備の必要性への影響は大変大きいと思います。次期事業化計画の検討に当たっては、人口減など、この間の社会情勢の変化等を踏まえて、改めて都市計画道路の必要性を検証するべきです。見解を伺います。
東京における都市計画道路のネットワークにつきましては、おおむね十年ごとに策定しております東京における都市計画道路の整備方針におきまして、必要性の検証が行われるなど、見直しが適時適切に行われております。また、直近では、平成二十八年三月に策定された整備方針におきまして検証が行われており、未着手の幹線街路を対象に必要性が確認されているところです。
次期整備方針の検討内容につきましては、今後、東京都と特別区及び二十六市二町とともに検討することになりますが、改めて都市計画道路の必要性が検証されるものと、区としては想定しております。
今後、必要性の検証が行われる場合は、担うべき交通量など様々な役割や機能を考慮した検証となるよう、東京都と特別区及び二十六市二町による検証に参画してまいります。
多額の税金が投入される事業です。必要性の検証は区民感情と乖離したものになってはならないというふうに考えます。
次に、都市計画道路補助五二号線についてです。
都市計画道路補助五二号線は現状、若林から宮坂間が事業中で、宮坂一丁目一二八号線から環八船橋までが優先整備路線となっており、二つのお寺の一部、二つの公園を潰して、四つの商店街を分断する路線です。地域コミュニティーが壊され、多くの住民が立ち退きを余儀なくされるものです。道路ができることによって低層の住宅を壊して、高層化、繁華街化に道を開くことが懸念されるとして、住民の反対の声が上がっています。
現在、都道五二号線に反対する会と優先整備路線の地権者、沿線住民有志の皆さんが、東京都宛ての署名に取り組んでおり、補助五二号線優先整備路線、宮坂一丁目一二八号線から環八の区間の選定を外すこと、まちづくりや道路計画の在り方について、東京都と住民との話合いの場を設けることを求める署名を行っていると聞いています。
補助五二号線については、一二八号線以西については、今、優先整備路線になっていますけれども、見直しをすべきと考えます。見解を伺います。
第四次事業化計画では、都区市町による適切な役割分担の下、東京都全体を捉えた将来像や広域的な課題に加え、地域で抱える交通課題の解決や安全性の向上など、地域的な課題なども踏まえて優先整備路線を選定しており、区内では、お話の補助五二号線を含む十か所の都施行区間と九か所の区施行区間が選定されております。
区内の都市計画道路の整備水準が低い状況にある中、区といたしましても、補助五二号線は広域的な道路ネットワークの整備のみならず、沿線全体の交通の円滑化、地域の通過交通の抑制、防災・減災の機能の向上など、区民の安全で安心な生活を支えるために必要な道路として認識しているところでございます。
次期事業化計画として優先整備路線の検討を行う場合は、道路整備に対する地域の多様な御意見があることを区としては踏まえつつ、道路ネットワークの状況や地域の課題などの視点におきまして、重要性、緊急性などを考慮した上で優先整備路線が選定されるよう、都区市町において協議してまいります。
他会派からも、おおむね十年の期間に着手もできない路線を優先整備に選定するのはいかがなものかという趣旨の議論があったと思います。参加と協働を区政の根幹に据えている世田谷区が、合意形成なしに進めてよいのかというのが問われるケースだと思います。見直しを重ねて求めます。
今後、道づくりプラン策定に当たっては、区民の声を十分に聞き、計画に反映していただきたいと考えます。さらに、次期事業化計画の策定に当たり、区民の声が反映できるよう、都ともしっかりと協議を行っていただきたいというふうに思います。見解を伺います。
区は、次期せたがや道づくりプランの検討に当たりまして、道路や交通環境に対する区民の意識や考え方を把握するため、現在区民アンケート調査を実施しております。今後は、道路整備に関する考え方や方針を骨子として取りまとめ、区民意見募集を行う予定です。また、優先整備路線などを含むせたがや道づくりプランの素案に対してもパブリックコメントを行い、その結果を踏まえて計画の策定を進める予定でございます。
都区市町で策定を行う、次期東京における都市計画道路の整備方針につきましては、現時点におきまして策定プロセスは未定でございますが、幅広く区民意見の把握に努めながら検討を進めてまいります。
優先整備路線で反対運動が起きているところがあります。先ほど述べました補助五二号線の一二八号線以西を優先整備路線から外すこととか、環八以西については優先整備路線に選定しないでほしいということ、さらに、補助五四号線の下北沢部分について、Ⅱ期、Ⅲ期について優先整備路線に選定しないこと、さらに、補助二一七号線の成城地区で烏山地域の甲州街道以北についても優先整備路線に選定しないでほしいと、さらに、補助二一九号線についても見直しを求める、そういった署名運動をされています。多くの住民の声をどう扱うのか、区の姿勢が問われます。こうした声をしっかり踏まえた計画策定を求めておきます。
次に、祖師谷住宅の建て替え事業についてです。
現在、祖師谷住宅では建て替え計画が進んでいます。工事期間は今後十五年と聞いており、四期に分けて行われます。第一期工事の区域の計画のみが今示されていますが、建物の配置が変わることにより、二百本を超える桜や紅葉などの高木を含む樹木の伐採が懸念されたため、この間、移植など積極的に既存樹木を残してほしいと求めてきました。
九月七日、解体工事説明会が行われましたが、既存樹木の伐採の準備工事がもう進んでいるようです。区は、樹木の保全に向けてJKKを指導してきましたけれども、一期工事では、かなりの樹木が伐採されてしまいます。さらなる保全を求められないでしょうか、伺います。
祖師谷住宅建て替えに伴う第一期工区の解体工事につきましては、九月七日に開催された解体工事説明会以降、中低木の伐採など準備工事が進んでいるところです。
区は、これまで世田谷区街づくり条例に基づく街づくり誘導指針などにより、既存の緑を可能な限り保全し、現在の良好な環境を継承するよう東京都住宅供給公社に求めてまいりました。
今回の第一期工事での伐採に際しましても、事前に現地を確認した上で、最大限樹木を保全するよう求めてきており、建物にかからず現状の位置に残すことができた樹木が十七本、高木移植が十三本となっております。団地の建て替え工事は四期に分け、令和二十年度頃までの長期にわたって行われる予定ですので、引き続きさらなる樹木保全を公社に求めてまいります。
また、やむを得ず伐採する場合においても、新たな植樹を行うことで風景への影響を最小限とするよう求め、最終的には既存樹木も含めた地上部緑化率三六%以上を確保し、緑豊かで良好な居住環境が形成されるよう、地区計画や関連法令等に基づきしっかりと協議、指導してまいります。
区も一定頑張っていただいているというふうに思いますが、既存樹木を伐採し、植樹をしたとしても、その木が育つまで長い時間がかかります。二百本近くの樹木が伐採されることは大変残念です。できる限り既存の樹木を生かした建設計画にすることを条件にするなど、より強い指導が必要だったのではないかと思わざるを得ません。
一期工事の解体工事説明会では、搬入と搬出の道路について、地域の方からは心配の声が上がったと聞いています。大型の車両や建材などの搬入の道路は、敷地内の保育園にも面しており、朝、夕の送り迎えで安全面での不安や、一期工事終了後に入居されても、何年もの間、工事の騒音で苦しまなければならないのかとか、どこに相談したらいいのか分からないなど不安が述べられていました。
また、九月七日の解体工事説明会の質疑の中で、開催状況をホームページや書面で周知する前に工事を始めないでほしいというような要望があったと聞いていますけれども、九月末には開催状況をホームページにアップするということでしたが、アップされていませんでした。周知前に工事を始めるのではないかと心配の声が私にも届きました。資材等の搬入道路の道路沿道で、特に一方通行を解除する部分の住民に個別説明をするという話もありましたけれども、説明せずに工事に入るのではないかと不安の声も聞いていました。昨日、十月八日付でアップされていましたけれども、JKKからの説明、回答が十分ではないというふうに感じます。
十五年間と長期間にわたる工事となるので、JKKの相談窓口を設置し、それを沿道や周辺の住民がどこに相談したらいいのか分からないということのないようしっかりと周知することなど、丁寧に対応していただく、それを区も求めていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。
解体工事時説明会の開催に際し、区といたしましては、公社からの情報をまちづくりセンターなどと共有し、自治会や公社敷地内の保育園、工事車両通行予定の沿道住民への周知を公社に求めるとともに、必要に応じ仲介を行う等、地域に丁寧に対応するよう調整してまいりました。
説明会開催結果の公開につきましては、一方通行を解除する区間に面する住民などへの説明を事前に行うこととしたため、説明会で回答した九月末頃より遅れたと聞いております。
また、団地建て替えに関する相談窓口につきましては、区も同様の意見をいただいておりまして、相談先が分かりやすくなるよう、祖師谷まちづくりセンター二階の情報コーナーの掲示を区といたしましても工夫してまいります。
工事が具体的に動き出す中、地域にお住まいの方々も、安全対策や防音、振動など不安に思われる方も多いかというふうに思います。引き続き地域の不安の声を受け止め、丁寧に対応するよう公社に求めてまいります。
十五年にもわたる工事への住民の不安や意見、これにしっかりと寄り添っていただくことを求めます。
次に、交通不便地域についてです。
このたび、区より世田谷区地域公共交通計画素案が示されました。区は、この間、公共交通不便地域を指定し、その解消に取り組んでいます。砧での実証実験を今年度も継続して行い、結果を基に各地域に展開を検討するとしています。
運転手不足が深刻化し、現状、運行本数を確保していくことが難しくなってきているという実態があると伺っていますけれども、バス路線を残すために、あるいは本数が少なくなっているというところもありますから、そういったところをしっかり支援する必要があるかと思うんですけれども、可能でしょうか。
現在、区では五つのバス事業者により八十二路線の路線バスが運行されており、区民の重要な移動手段を担っています。委員お話しのとおり、利用者の落ち込みや運転手不足問題など、公共交通を取り巻く状況は年々悪化している中、バス事業者からはバス路線の再編やダイヤ改正、運転手の効率的な配置などを実施し、地域の足である路線バスを維持していくために対策を進めていると伺っています。
バス路線の維持には、自車利用から公共交通の利用に転換していただくなど、まずは、地域の皆様にこれまで以上に積極的に路線バスに乗っていただくことが第一と考え、区では、区のホームページやSNSなどを活用した利用促進に加え、バス停ベンチ、上屋の環境整備を図ってまいりました。
また、さきにお示しした世田谷区地域公共交通計画素案においても、交通ネットワークの確保・維持・拡充を施策の一つに掲げており、持続可能な地域公共交通を目指し、バス事業者の意見を聞きながら、都市計画道路やバス待ち環境の整備促進、バス利用促進イベント等の参加、支援など、バス路線を維持するための効果的な行政支援に取り組んでまいります。
そうですね、利用していただくということが、その維持にもつながるというお話です。芦花公園駅踏切を通過する千歳烏山駅と成城学園前駅の区間の路線があるんですけれども、これはとうとう一日二本にまで減ってしまいました。高齢者や障害者などにとって、行動が制約されるということが、これは明らかです。路線がなくなれば移動が困難になって、通院も買物も、そして社会活動も困難になります。区は、交通不便地域の解消には福祉的な視点で取り組むとしていますし、今度は、住民も自ら支えるという観点もしっかり持ってやっていただくということで、これはアピールが本当に重要になってくるというふうに思っております。
世田谷区地域公共交通計画素案では、公共交通不便地域の解消に向けて地域協議会を立ち上げるということが書き込まれました。区民、行政、事業者が連携して考える場は重要です。これをどのように区は進めるのか伺います。
公共交通不便地域対策の推進につきましては、世田谷区地域公共交通計画素案において施策の一つに掲げており、地域の状況を踏まえたコミュニティー交通の導入、検討に取り組んでいくこととしております。令和七年三月の本計画策定後は、速やかに他地域への展開に向けたガイドラインとなる手引をお示しし、新たな交通サービスの実証、導入に向けた手順など、各総合支所でオープンハウス等により周知の上、各地域の意見や状況などを確認しながら、順次取組を進めていきたいと考えています。
また、現在公共交通不便地域対策として取り組んでいる砧モデル地区の実証運行では、地元協議会の皆様をはじめとした地域や運行事業者、まちづくりセンターなどと連携しながら、地元町会のチラシ回覧や地元商店でのポスター掲示、スマホによる予約講座など、幅広く広報活動の取組を進めることで、多くの方の御利用に結びついています。
他地域への展開におきましても、砧モデル地区での検証結果を踏まえ、地域と連携しながら、地域協議会の早期設立を促進するなど、公共交通不便地域の解消に向けた取組を進めてまいります。
ぜひ、他地域への展開を進めていただきたいと思っております。
区議になって十年目ですけれども、この間、烏山地域の北烏山一丁目、粕谷、上祖師谷の方から、バス路線をつくってほしいと、便を増やしてほしいと、こういった要望を受け続けてきました。なかなか実現できないということで、自分が生きているうちには実現しないのかと言われることもあります。特に、高齢者、障害者にとっては切実です。
今、六所神社前通りの道路整備が進みつつあります。上祖師谷地域の交通不便地域解消に向けて、区はどのように取り組むのか伺います。
委員お話しの上祖師谷地域におきましては、現在路線バスが運行していない地域であり、六所神社前通りの整備完了後も、周辺の京王線連続立体交差事業や千歳烏山駅前の交通広場が整備されるまでの間、路線バスの運行が厳しいことから、公共交通不便地域の解消には、ワゴン車両を活用したデマンド型交通などの検討が必要であると認識しています。
現在、世田谷区地域公共交通計画の策定と併せて、公共交通不便地域の定義の見直しを行い、その中で、改めて公共施設圏域や人口特性などを踏まえた重点検討地域を別途設定することとしております。
重点検討地域に選定された地域におきましては、本計画策定後にお示しする新たなコミュニティー交通を導入するためのガイドラインとなる手引を基に、お住まいの皆様の意向や機運などを確認した上で、区民、交通事業者、区が協働、連携しながら、公共交通不便地域対策を進めていきたいと考えております。
区といたしましては、公共交通不便地域対策の推進に向け、地域の状況を踏まえたコミュニティー交通の導入、検討に取り組んでまいります。
この交通不便地域解消も、本当に参加と協働だというふうに思います。多くの住民が、この協議会、区が予定しているそういった活動に参加しやすいような工夫を、ぜひ今から検討していただきたいということを申し述べておきます。
次に、区営住宅の質の向上を求め伺います。
住まいと寿命の関係について研究論文が今年発表されました。この論文を紹介した記事によると、持ち家、公営住宅、民間の賃貸住宅などに住む方の寿命を調査したところ、一番長寿だったのが持ち家に居住している方、その次は公営住宅、その次が民間の賃貸住宅であったといいます。同じ賃貸でも、民間より公営住宅のほうが生活の質を高く保持できるということでした。公営住宅が住民の健康を守るという役割を担っていたのだと、改めて実感しました。現在、第四次住宅整備後期方針策定の過程にあります。特に区営住宅の質の向上について伺っていきます。
まず、現在進められている第四次住宅整備後期方針策定に向け、見直しの中で居住者の健康を守るという視点、これが非常に重要かというふうに思っております。ぜひ、ここに向けた取組などを充実させる必要があるかと思いますが、いかがでしょうか。
現在、第四次住宅整備方針に基づき、公営住宅における建て替えの際には、子育て世帯や高齢者、障害者などの多様な住まい方に対応できる良質な住宅の供給を事業者へ要請しております。
また、区営住宅などにおける維持保全に関しましても、世田谷区公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存住宅の維持管理や建て替え再編などを検討する際には、他の公営住宅と同様に、良質な住宅の確保と供給を図ることで入居者の健康を守るための整備を引き続き進めてまいります。第四次住宅整備後期方針策定に向けても、良質な住宅の確保という視点も欠かさずに見直し作業を進めてまいります。
これは本当に重要だというふうに思います。この夏も熱中症により救急搬送された方、亡くなった方がたくさんおられます。地球沸騰化と言われる中で対応して断熱化を進めるなど、ZEH化は当然ですが、今や賃貸住宅ではスタンダードになっているエアコン設置など、これを標準仕様にする必要があるんじゃないでしょうか。区営住宅の仕様変更を行って、居住者の生活の質を高めること、これを位置づけるべきかと考えますが、いかがでしょうか。
良質な住宅の提供や環境負荷低減を目的とし、一部の公営住宅などでは壁面緑化や屋上緑化とともに、サッシ改修により断熱効果を高めるなどの取組を実施しております。さらに、本年度より既存住宅の維持管理における屋上防水の改修の際には断熱塗料を使用し、室内温度の上昇を抑えるなどの取組も新たに実施する予定となっております。
委員のお話の住戸のエアコン設置に関しましては、家電製品であるため居住者の負担となっておりますが、今後も引き続き、既存住宅の改修工事の際は環境に配慮した材料を選定するなど、先の取組を進めてまいります。また、区営住宅などの建て替えの際は、ZEH水準の仕様とするなど、環境負荷低減を目指すことで、居住者に良質な住宅の提供を図ってまいります。
今や民間ではエアコンのない共同住宅というのはほとんどないかと思われます。エアコン設置は大家さんがやるわけですけれども、区営住宅は大家は世田谷区だと思うんですね。しっかりその観点は入れていただき、公共住宅ではそういう基準にはなっていないかと思います。しかし、沸騰化と、人が死ぬぐらいの勢いで本当に気候変動が進む中、区民の命を守る、健康を守るという観点をお持ちなんですから、ここについて、ぜひしっかりと検討をしていただきたいというふうに思います。
次に、区営住宅の応募倍率についてちょっと伺います。
区営住宅における入居者の募集は六月と十一月の年二回行われており、令和三年から令和五年の三年間の募集倍率は、住宅の種類にもよりますが、平均で十四倍程度となっており、高齢者向け住宅に関しましても同程度の倍率となっております。
今、住まいの貧困というのが社会問題化しています。高齢者や障害者、シングルマザーなどへの入居拒否、安心して家賃を払えないために住まいを失う若者というのが増えています。日本の住宅支援は大きく立ち遅れているという状況があります。政府は長く住まいは自助努力でと持ち家政策を進め、公共住宅の整備を怠ってきました。区民の住まい確保に責任を持ってこなかったことが、住まいの貧困を生んでいます。低所得者、高齢者、障害者、若者などが安心して暮らせる住宅は圧倒的に不足しています。
住生活基本法は、住宅は国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤とし、低所得者、被災者、高齢者、子育て世帯などの住まいの確保を掲げています。国はその立場に立ち、公共住宅の拡充を図っていくと。国の責任による恒久的な家賃補助制度の創設が求められるというふうに思います。今、住まいの貧困への対処として、当区としても、区営住宅を増やしていくということ、これが必要ではないかと考えます。検討していただくことを求めて質問を終わります。