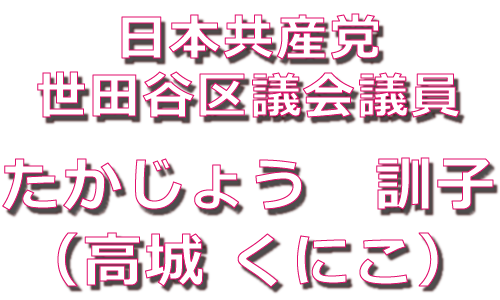

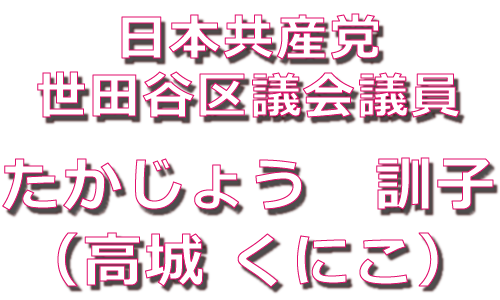

2024/11/28
通告に基づき、伺います。
まず、旧林愛作邸を含む敷地の土地利用についてです。
区は現在、フランク・ロイド・ライト設計による旧林愛作邸とその周辺の池や庭を文化財として現地で保存する方針を立て、敷地所有者である住友不動産と土地利用を含めた協議を進めています。この間、会派として、フランク・ロイド・ライト作品である旧林愛作邸の適切な保存を求めてきました。一方で、旧林愛作邸の保存を理由に、周辺住民の住環境を損ねるような建築制限の緩和には反対してきました。九月の常任委員会では、旧林愛作邸の保存と活用に向けた土地利用の基本的な考え方が示され、その後、十月十八日、二十日に周辺住民への説明会が開催されました。
住友不動産は、旧林愛作邸を現地で保存するためとして、建築の高さ制限を現行の十メートル以下から二十五メートル以上に緩和することや、建蔽率や容積率の緩和を目的とした用途地域の変更を求めています。特に高さ制限の緩和については、現行では三階から四階建てが限界ですが、二十五メートル以上となると八階建て以上の建築物が可能になってしまいます。また、住友不動産は一団地申請を行うことも想定しています。これにより、敷地内に設置予定の道路は敷地内通路となり、道路斜線の制限が適用されなくなります。その結果、大規模な建築物となる可能性があります。建築制限の緩和による周辺住民の住環境への影響は大きいものと考えます。
住民からは、高さ制限を緩和しないでほしい、高い建物になれば住環境の破壊につながる、具体のプランを示してほしいとの要望が上がっています。区は、事業者の利益を優先するのではなく、周辺住民の住環境を守る立場に立っていただきたいと思います。
区は、住友不動産が求める高さ制限や用途地域の変更を全て受け入れる方針なのか、区が建築制限の緩和の必要性を判断した根拠、また、その影響をどのように検討したのか伺います。
区は、住民説明会で示された、特に高さ制限の緩和による住環境の悪化の懸念、事業計画の資料を求める声にどう応え、どう進めるのか伺います。
次に、就学援助の拡充についてです。
現状、区内では五年前と比べ子ども食堂が二倍になり、利用者が三倍になるほか、フードパントリー利用者が増加するなど、食べるにも困る状況が増えていることが確認されています。こうした中、子どもが経済的な理由で学用品をそろえることができないということのないよう、教育費負担のさらなる軽減が必要です。二〇二四年十月における文房具の消費者物価指数は、二〇二〇年を百としてみると百十三・四、学用品費は上昇しています。区の就学援助の学用品費については、財調の基準単価よりも低いことが分かり、昨年同額に引き上げたと伺っています。しかし、財調の基準単価自体の見直しについては平成二十七年以降行われてきませんでした。
この機会に就学援助における学用品費を実態に即したものに見直すことを求めます。見解を伺います。
品川区では、この四月から学用品費の無償化を実施し、葛飾区では修学旅行費用の無償化に踏み切りました。
この間、我が会派は、まずは子どもの貧困対策として、経済的に困難な家庭への支援である就学援助を拡充することも求めてきました。第三回定例会では、修学旅行費用の無償化を実施することとともに、就学援助の支給範囲を拡充することなどを求めてきました。
世田谷区令和五年度決算での実質収支は約百十一億円となりました。毎年、百億円以上です。年度末における基金残高は約一千四百七十億円で、特別区債残高四百八十一億円で、引き続き区の財政は健全な状況です。教育の機会均等、給食費を含む義務教育の完全無償化は憲法二十六条の要請です。その一歩となる給食の無償化に区も踏み出し、アレルギーや宗教上の理由などで給食を食べることができない場合の給食費相当分の支給や、学びの多様化学校での給食の開始などにも取り組んできました。
さらに、義務教育の完全無償化実現に向け、国に財源を求めることや、無償化に向けた本格的な検討も進めるべきと考えます。区は、義務教育の完全無償化を図る意義についてどのように考えているのか伺います。
次に、子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策について伺います。
区は、東京都が行う子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策を受け、施設に対する支援を行う補正予算を示しました。補助額算定の根拠について、東京都からははっきりした回答が得られなかったと伺っています。私立保育園の園長からは、補助額は食材費の値上げ分にしかならない、光熱費も含め他の物価高騰分には足りないと伺っています。
子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策の補助額が適切であるか、現場の声を聞き、必要であれば区独自の上乗せなど検討する必要があるのではないでしょうか、見解を伺います。
話を伺った園長からは、保育士の人材確保がさらに困難になっていると伺っています。報道によると、十一月二十二日、こども政策担当大臣は、閣議決定された総合経済対策に、保育士と幼稚園教諭の給与を一〇・七%引き上げる処遇改善策を盛り込んだと発表しました。
区は独自に今まで保育の質確保のために保育士一人当たり一万円の支援を行ってきましたが、今回の国の処遇改善策が実施の際にも、さらなる保育の質向上を目指すため、支援を中止することなく継続していただきたい。見解を伺います。
最後に、北烏山七丁目緑地について伺います。
北烏山七丁目には、岩崎学生寮周辺の大規模な樹林地が残されています。平成十四年と十五年に地域住民の皆さんが区に対し、緑の保全を求め、一万筆の署名を提出しました。これを受け、区は三・三ヘクタールの貴重な樹林地を複数年かけて取得し、緑豊かで良好な地域の環境を守るため、令和十年度完成を目指し、樹木の保全や公園整備を行います。この間、私は公園整備に当たって、地域住民の参加と協働で進めることを求めてきました。区は、ワークショップ、オープンパークを行い、住民同士が意見を出し合い、考える場や、住民自身が公園づくりに関われる支援を行ってきました。私が傍聴した七月のワークショップでは、防災拠点として、災害時に緑地に集まり、地域の人が利用できるようにするために日頃から防災につながるように使いたい、子どもの遊び場として地域に子どもの遊ぶ場が少ないので期待したいなど活発な議論が行われました。十月にもワークショップが、十一月にもオープンパークが行われています。私自身も周辺住民からは、災害時に住民が集まれて、煮炊きができる室内施設ができないか、できるだけ樹木を残して生態系を維持してほしいなど要望を伺っています。地域住民の公園整備への期待は大きいと感じています。
都市整備方針(素案)では、まちづくりへの子どもの参加について述べられています。積極的と評価しています。今般の公園づくりにおいても子どもの意見を取り入れることはもちろん、公園づくりに参加できるよう支援に取り組んでいただきたいと思っています。
区は、北烏山七丁目緑地整備において、緑地の利活用の検討及び官民連携手法による公園整備の導入の検討などを進めるとしていますが、今後、子どもを含めた周辺住民の声をどう反映し、どう運営していくのか、伺います。
以上で壇上からの質問を終わります。
私からは、旧林愛作邸を含む敷地の土地利用について、二点御答弁いたします。
まず、区が建築制限の緩和の必要性を判断した根拠、また、その影響の検討についてでございます。
区は、旧林愛作邸を現位置で保存する意義と、所有者からの要望、住民説明会での意見などを踏まえ、本年八月に駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方を取りまとめてございます。歴史的建造物を保存する土地利用の考え方として、地域資源の魅力を高めることとして、周辺の池などの庭園を含む建物周囲の敷地を含め、文化財保護制度に基づく文化財指定に取り組むこととしております。その上で、建物周囲の敷地も含めた現位置保存を前提として、都市計画諸制度の活用を検討することとしてございます。
都市計画諸制度の活用に当たりましては、本来、旧林愛作邸周囲の敷地に建築できる床面積を地区内で確保するための検討を挙げており、用途地域や高度地区の変更などにより、土地の高度利用と本地区周辺への影響を考慮した建築計画を誘導するものとしてございます。
高度地区等の変更については、周辺への影響などを十分に考慮した斜線制限や壁面後退など一定の制限の下、総合的に検討するべきと考えております。来年度より地区計画の策定に向けた周辺住民を対象とした懇談会等を開催し、住民や所有者の意見を聞きながら丁寧なまちづくりに努めてまいります。
次に、住民説明会の声にどう応え、進めるのかについてお答えいたします。
土地利用の基本的な考え方では、歴史的建造物を保存する土地利用の基本的な考え方のほか、周辺環境に配慮する土地利用の基本的な考え方を併せて示してございます。その中で、都市計画諸制度の活用について、総合的に検討するものとして、高度利用を図りつつも、周辺住宅への圧迫感の低減及び日照、プライバシーの配慮、周囲の隣接地から後退した建築物等の配置や斜線制限について明記をしてございます。
現時点では保存する敷地の範囲等が定まっていないため、緩和や制限の具体的な検討に至ってございません。今後、所有者と区との協議の中で、専門家等の意見も伺いながら、保存する敷地の範囲等についての検討を進め、住民に説明をしてまいります。その上で、地区計画の懇談会等の中で住民がイメージしやすいボリューム図などを用いて、緩和や制限内容の案について説明するなど適宜対応を行ってまいります。
区としては、現位置保存を前提と考えており、この間の住民説明会でも旧林愛作邸の歴史的価値や、現位置保存の意義等についても様々御意見をいただいてございます。住民の方々に、現位置保存の考え方とともに、土地利用の基本的な考え方への理解を深めていただける取組を所有者とも協議を重ね、進めてまいります。
以上でございます。
私より、二点について御答弁いたします。
まず、就学援助における学用品費の見直しについてでございます。
物価上昇が続いている昨今の社会経済情勢は区民生活に様々な影響をもたらしており、教育に係る保護者の経済的負担もできるだけ軽減することが望ましいと認識しております。
就学援助では、所得基準を設けた上で、学用品費をはじめ、新入学用品費や修学旅行費などを支給しており、この間、対象世帯の拡大や支給金額の見直し、支給時期の追加など、支援の拡大、拡充に取り組んでまいりました。
学用品費の見直しにつきましても、都区財政調整における積算基礎単価の見直し状況のほか、他自治体の動向なども注視しつつ、区長部局とも連携しながら引き続き検討してまいります。
次に、義務教育の完全無償化を図る意義についてお答えいたします。
この間、区では、区立小中学校の給食費無償化など、物価の状況、少子化対策としての経済支援の側面などから、国や都に先んじて優先的に支援すべきと判断したものについて実施してきましたが、本来、国が実施すべきものであり、区としても、国が実施するまでの間、継続する方針としたところでございます。
教育委員会といたしましては、子どもたちに対する教育は社会経済情勢や家庭環境などに左右されることなく、ひとしく保障されるものであると考えております。このことからも、教育の無償化については自治体の財政状況によって格差が生じるべき内容ではなく、まさに基礎的、かつ重要な施策であることから、国が少子化対策の面も含め、その制度設計等を実施すべきものと考えております。
この間、この考え方に基づき、特別区長会を通じ、国に対し早期の給食費無償化実現を求めておりますが、国においては、教員の働き方改革の議論が活発になっていることや、こども家庭庁から各政策が示されるなどしており、議論が活発になっております。引き続き国の動向を注視してまいります。
以上でございます。
私からは、二点御答弁いたします。
初めに、子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策の区独自の上乗せについてです。
区では、東京都が補正予算にて新たに実施する物価高騰対策の補助制度を活用し、子ども・子育て関連施設への物価高騰緊急対策として補正予算案を御提案しているところでございます。
物価高騰緊急対策では、東京都の補助制度を有効活用する観点から、補助基準額は東京都が示した単価を用いて計上しております。一方、物価高騰緊急対策で最も規模が大きい認可保育園では、運営費に当たる公定価格は、毎年度、国の人事院勧告や物価等を考慮して定められており、令和五年度は四・九%程度の大幅上昇となっております。
区としましては、子ども・子育て関連施設の物価高騰の影響に対しては、国や東京都の様々な支援策や公定価格の上昇により対応が図られているものと認識しておりますが、引き続き現場の声を伺うとともに、物価の状況や国、東京都の動向などにも十分注視し、子ども・子育て関連施設への運営に大きな影響が見込まれる場合には、関係所管とも連携を図りながら、時期を逸することなく必要な対策を行ってまいります。
次に、区独自の処遇改善についてです。
区ではこの間、保育施設の人材確保を支援するため、宿舎借上げ支援事業や、議員御指摘の区独自の一万円の助成などの処遇改善に取り組んでいるところでございます。また、こうした取組に加え、事業者の人材採用活動を支援するため、保育人材情報ポータルサイト、せたがやHoiku Workによる求人公開、区内外の就職相談会の実施、保育士養成校の訪問による学生へのPRなど様々な対策に取り組んでまいりました。こうした取組は、区内保育施設の人材確保に一定の効果を上げているものと認識しております。
しかし、この間、保育待機児童の解消を図るため、区内の保育施設の整備が進んだことや、国全体の人材不足の影響もあり、多くの保育施設ではいまだ人材確保に苦慮しているとの声をいただいております。各保育施設が安全で質の高い保育を継続して実施していくためには引き続き保育人材確保の取組は必要であると考えており、議員御指摘のとおり、国による保育士等の処遇改善案が示されておりますが、区としましては、国や都に対し、人材確保につながる事業の継続の働きかけを行うとともに、御指摘の区独自の一万円の処遇改善助成金も含め、予算編成の中でしっかりと検討してまいります。
以上です。
私からは、北烏山七丁目緑地の整備についてお答えいたします。
(仮称)北烏山七丁目緑地については、令和五年度に策定した緑地整備の基本的な考え方を示した基本構想において、地域との協働による緑地づくりを進めていくこととしております。令和六年度からは、この基本構想を踏まえ、ワークショップを二回、緑地開放イベント二回、加えてアンケート調査などの多様な手法により地域の方々の声をお伺いしながら、緑地の基本計画づくりを進めているところでございます。
ワークショップなどでは、今ある自然資源を残してほしい、計画段階から緑地の維持管理に関わっていきたいなどの御意見や、官民連携手法による公園施設について、飲食や活動拠点に関する御意見などをいただいているところでございます。
引き続き、ワークショップや緑地開放を継続し、新たに子どもの声を直接聞くための子どもワークショップを開催するなど、計画づくりに対して、より幅広い世代の方々の声を聞く工夫を講じてまいります。また、開園後を見据えて、将来の緑地管理に携われるような仕組みづくりに向け、地域の方々による様々な活動の試行を重ね、その成果を今後の計画づくりへと反映してまいります。
以上でございます。
北烏山七丁目緑地の利活用や官民連携手法について意見を申し述べます。
さきの都市整備常任委員会で、玉川野毛町公園における便益、サービスの拠点になる施設をパークPFIの手法で行うということで、事業者の選考を進めてきましたけれども、事業者一社、応募してきたのは一社なんですが、辞退したと聞きました。
そもそもパークPFIは民間の利益を前提とする仕組みですから、利益を見込めなければ民間は撤退します……。