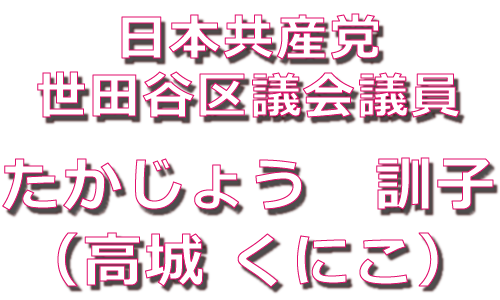

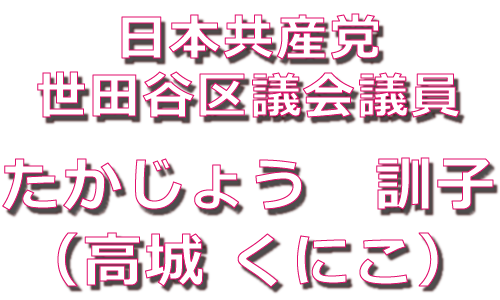

2024/10/01
日本共産党の質疑を始めます。
まず、代表質問に続き、豊かな財政基盤を生かした暮らしを守る区政運営を求め、伺います。
子どもの食の支援についてです。コロナ以降、この間の物価高騰の中、子ども食堂等の利用が増えるなど、生活困窮世帯の広がりが顕著になっています。代表質問でも紹介しましたけれども、子ども食堂を運営している方からは、利用希望がキャパを超えている、待ってもらっている方もいると。ひとり親の状況が深刻なため、ひとり親家庭を対象としたフードパントリー支援も実施していると。夏休み中、学童に持っていく弁当を作る食材がない、何とか分けてもらえないかと利用者から連絡が入って急遽対応したとか、貧困の質がコロナ前と明らかに違うというふうに伺っています。この五年間に子ども食堂は二倍以上に増え、利用者も三倍以上に増えています。
区は、子ども配食事業、KODOMOぱくぱく便や食の支援サポーター派遣事業に取り組んでいますが、その実績、現状はどのようになっているのか伺います。
区では、子どもの心身の健康の増進や家庭の生活の安定を図るとともに、支援を必要としている家庭が地域の支援につながることを目的としまして、令和元年七月より食の支援サポーター派遣事業と子ども配食サービスを実施しております。
ひとり親家庭や保護者の疾病など、様々な理由から、結果的に子どもの孤食や栄養の偏りといった食に関する課題を抱えていると子ども家庭支援センターが判断した家庭を対象に、令和五年度は、食の支援サポーター派遣事業は六世帯、延べ百十一回、子ども配食事業は、五十八世帯、延べ一千四百十七回御利用いただいております。
事業を利用したことで食事作りの負担が軽減され、また、バランスのよい食事を受けることができたという声のほか、支援者に相談しやすくなったといった声も伺っております。
非常に重要な支援で、この二つの食の支援は、貧困や養育困難など支援が必要な家庭を区の今ある支援につなげるための窓口になる役割を果たしていると認識しています。
子どもの配食サービスの令和元年度から令和五年度までの実績を見ると、令和元年度には十四世帯、令和二年度は、コロナ感染拡大により学校が休業した際に区が行った配食事業が含まれるため、百一世帯、その後、令和三年度からは対象を広げていただいたことにより六十九世帯、令和四年度は五十二世帯、令和五年度は五十八世帯と、コロナ前より増えているという状況です。しかし、利用者が増える一方の子ども食堂に比べると増え幅が少ない状況です。
基本、子ども家庭支援センターの判断で必要な支援につなげていると伺っていますけれども、子ども食堂から食の支援などにつながったケースというのはごく僅かです。子ども食堂の連絡会などを通して実態を把握し、さらに支援につなげる取組が必要ではないかというふうに思います。
認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、首都圏、近畿圏、九州にて、低所得のひとり親家庭を対象にした食品支援事業、グッドごはんを展開しています。多くの寄附により、今年の五月時点で延べ八万二千七百三十一世帯に食品を配付しているという団体です。本年三月に同法人が実施したアンケート調査の結果から、学校給食のない長期休みの期間に一日三食を食べられない子どもがふだんの三倍以上にも増えるということが明らかになったことを受けて、学校給食のない夏休みに家庭で十分な食事を取ることが難しく、困難なひとり親家庭の子どもたちに対し、この夏、ふだんの二倍の食品を配付する、こういった緊急対策を開始したということです。
給食がなくなる夏休みに、例えば就学援助受給世帯の希望者に子どもの配食サービスを活用する。さらに、週一回では不十分であることから回数を増やす。また、学童に通う子どもの家庭でお弁当注文を採用している家庭に弁当相当額を支給する、お弁当注文を採用していない学童の子どもには弁当を配食するなど、特別の支援を行う必要があるのではないでしょうか。実態把握を行い、実情に合った事業規模など事業の拡大等を検討していただきたいというふうに思っております。見解を伺います。
区ではこの間、子ども食堂の利用者で支援が必要な方に気づいた場合は子ども家庭支援センターに連絡をいただき、互いに連携を取りながら、食の支援事業をはじめとする区の支援につなげております。また、子ども家庭支援センターから子ども食堂への見守り依頼をしながら支援をする場合もあります。
委員お話しの夏休みにおける食の課題は、必ずしも学童の利用者だけに限らないと認識しており、今後も子ども家庭支援センターが子ども食堂の連絡会等に出向くなど、子ども食堂を利用する家庭の実態の把握に努めてまいります。
食の支援事業は、個々の家庭に関わりながら必要な支援につなげるきっかけづくりの事業であり、お話しのような特別な支援は別途の議論が必要なものであると認識しております。困難な状況にある子どもや家庭が食の支援事業につながった際は、丁寧に関わり、それぞれの子どもや家庭の状況、ニーズを捉え、子ども家庭支援センターと連携しながら、子どもや家庭を取り巻く状況を踏まえた適切な支援につなげてまいります。
今、食に困るというケースがすごく増えているという状況が見られます。今の食の支援は、生活困窮や養育困難の家庭で、支援を受けることにためらいがある方でも抵抗が少ない食の支援を入り口にして、区の様々な支援につなげていくためのツールという位置づけになっています。これは虐待防止であるとか、そういったより困難度が高い家庭を支援につなげるという点でも大変重要と認識しています。ゆえに利用は限られます。その他の子ども食堂やフードパントリー等の利用となるかと思います。
しかし、区が支援している子ども食堂やフードパントリーも、地域によっては月に一回のところもあるし、キャパオーバーになっているという状況があります。また、地域偏在もあります。フードパントリーは区の支援だけでは足りず、企業からの支援を受けるなど取り組んでいますけれども、やはり足場が不安定です。今の制度の立てつけでは、給食がない長期休みの食の問題を含め、増加する食に困る子どもたち、家庭の多くは利用ができません。支援からこぼれ落ちている可能性があるというふうに思います。自治体の役割をぜひ果たしていただきたいというふうに思っております。
御答弁のとおり、子どもの実態を都度都度、機敏に把握する必要があると思います。そして、今ある支援が十分なのか、何が足りていないのか点検していただきたいと思います。その上で必要な施策を展開していただきたいと重ねて求めておきます。
次に、来年度予算に向けた子どもの貧困対策の充実を求め、区長に伺います。
来年度から始まる子ども・若者総合計画(素案)が示されています。政策の七つの柱のうちの五番目、子ども・若者が、障害の有無、生まれや育ちの環境に関わらず、安心して育つことができる地域をつくりますの項目では、ポジティブな体験を重ねることができる環境づくりを進める必要があり、そのためには様々な課題や個別ニーズに応じ、必要な支援が受けることができるよう施策を充実すると述べられ、こうした施策により、子ども、若者一人一人が障害の有無や家庭の経済状況など、生まれや育ちの環境で選択肢が制約されず、本来持っている力が発揮できるよう、ウェルビーイングな状態にあることを実現するとしています。
この方針の実現に向け、具体には、ただいま述べましたけれども、子ども食堂のニーズがキャパを超えてオーバーフローになっている状況への対応や子ども食堂から支援につなげる仕組みの強化、給食がなくなる夏休みの食の支援など、こういったことも検討する必要があると考えています。また、教育分野では、代表質問で求めた修学旅行費の無償化、これを例えば修学旅行費への支援を以前の給食無償化ラインの世帯まで無償にした場合は対象は四百人増で、二千七百万円の増額で実現可能です。就学援助の支給範囲を生活保護基準の一・四倍を一・五倍へと引き上げた場合は四千万円の増額で実現が可能です。
子どもをめぐる状況というのは悪化しています。今必要な支援にしっかりと取り組んでいただきたく思います。来年度予算に向けて子どもの貧困対策をどのように進めるのか、区長の考えを伺います。
たかじょう委員に、子どもの食についてお答えをいたします。
令和五年度に高校生世代の子どもと保護者を対象とした調査結果では、経済的な理由によって生活困難を抱えるお子さんの割合が一五・四%であり、物価の高止まりなど、昨今の社会経済情勢は区民生活、とりわけ、子ども、子育て家庭に大きな影響を与えており、子どもの貧困対策の推進が求められると考えております。
区ではこの間、福祉・教育部局をはじめ、関連部署から成る子どもの貧困対策推進連絡会を通じて全庁的に子どもの貧困対策に取り組んでおりまして、現在は子ども・若者総合計画(第三期)に内包する次期子どもの貧困対策計画を検討、策定をしようとしているところでございます。
夏休みの日数を短くしてほしいという声が上がるなど、子どもの貧困の中には物質的な、あるいは食の貧困だけではなくて体験の格差、これも顕著なものになってきているということも注目しなければならないと考えております。
次期子どもの貧困対策計画の素案において、目指すべき状態の一つとして、親の妊娠、出産期から子どもが若者となり、卒業、就職して、社会的自立が確立されるまでを見据えて、生活困難を抱える子ども、若者や、その保護者の衣食住をはじめ、生活の安定に向けた支援の充実を掲げております。
子どもの現在及び将来が生まれ育った環境に左右されることがないよう、そして、目下の子どもの貧困の厳しい現実の解消に向けて、子どもの権利を保障する切れ目のない子どもの貧困対策に今後一層取り組んでまいりたいと思います。
本当に子どもの実態を都度都度把握していただきたいというふうに思います。子ども・若者総合計画の策定の中で、今ある支援が十分なのか、何が足りていないのかということを本当に点検していただきたいということを、そして、必要な施策を展開していただきたいということを重ねて求めておきます。
次に、駒沢一丁目地区、旧林愛作邸の保存、土地利用の考え方について伺います。
区は、当該地区において平成二十七年、二〇一五年に街づくり誘導指針を策定しました。これは、この時期に大規模な土地利用転換が想定されたことから、旧林愛作邸の保存や周辺環境に配慮した建築計画を誘導するために策定されたものです。ところが、令和三年、二〇二一年に現所有者である住友不動産株式会社が当該地区を取得すると、区は協議を重ね、今般、旧林邸の保存のために、用途地域や高度地区の変更で建築制限の緩和を行っていく考えを示しました。これは住友不動産からの要望などが上がっているということからということで伺っています。住友不動産は、誘導指針や今の建築制限の内容を承知で当該地区を取得しており、本来ならば、それを踏まえた建築計画とすべきだと考えます。我が会派は、建築制限を緩和する合理的な理由はないと考えています。
七月に行われた周辺住民との意見交換会では、区が示した当該地区の用途地域や高度地区を変更する考え方などについて、低層の住宅が広がる地域に高い建物が建つのではないかとの不安の声、反対の声が上がったと伺っています。それは当然のことだというふうに思います。フランク・ロイド・ライトの建物の保存が重要であるということは御説明いただいていまして、理解はしても、保存のために生活環境を諦めろというのはなかなか納得がいかないというふうに思います。
また、旧林邸の活用について、国民共有の財産にふさわしい在り方を所有者とともに検討するとしていますが、建築規制の緩和に向けた積極的な動きだけが先行しており、どのような保存を行うのか、何を大事にしていくのかは全く分かっていません。
旧林邸は近代建築の三大巨匠の一人、フランク・ロイド・ライトの建築物です。日本に存在する四つの作品のうち彼が日本滞在中に完成したのはこの林邸だけ。ほかの三つの建築物のうち二棟は重要文化財、一棟は登録有形文化財ですが、フランク・ロイド・ライトが帰国後、弟子が仕上げたとされています。このことからも林邸の保存はより重要です。保存の考え方には、建物周囲の敷地も含め、文化財保護制度に基づく文化財指定に取り組むとしていますが、周辺の池等の庭園を含む現位置での保存を前提というふうに書いてあります。建築物に隣接する池の南側の広場については保存の対象としないのではないかということが前提のように見受けられます。
私は八月に行われた現地の見学会に参加してきましたけれども、大広間の南側の開口部からの眺めがすばらしくて、この眺めも設計、デザインの一部なのではと感じました。建物と周辺の池等の庭園のみを残すような記載がされていますけれども、その考え方が適切であるのか、複数の専門家でしっかり見極めることが重要だというふうに思います。
旧林邸の具体的な保存、活用計画を所有者任せにしてはならないというふうに考えています。旧林邸の保存、活用計画に区はどういった役割を果たしていくのか、どのように関わっていくのか伺います。
旧林愛作邸の文化財としての重要性を鑑みますと、所有者の意向も踏まえた上で、国民共有の財産としてふさわしい保存活用が図られるべきであると認識をしております。
文化財保護制度による保存を前提とした所有者との今後の協議に当たっては、文化財保護に関する学識経験者の知見に加え、東京都や文化庁の意見も踏まえて助言や提案を行うこととしてございます。
区民の皆様が旧林愛作邸の文化財としての価値を共有できる保存、活用に向けて、所有者が行う保存活用に関する計画策定への協力、支援に鋭意努めてまいります。
我が会派の坂本委員のさきの一般質問での答弁で、専門家の意見を聞くというふうに答弁されていますが、具体的には、どのような人から話を聞くのか、また、その意見はどういった場で所有者に伝えるのか伺います。
フランク・ロイド・ライトは世界的な建築家であることから、国内にも専門的な研究者は多数いらっしゃいます。一方で、旧林愛作邸が貴重な文化財であることから、保存、活用に関して助言いただく専門家としては、文化財保護審議会の委員やその経験者など文化財建造物の保存に造詣の深い複数の学識経験者が望ましいと考えてございます。
今後、こういった学識経験者の助言をいただく場を設けるとともに、区民や区議会の皆様の御意見も踏まえながら教育委員会としての考え方を整理し、専門家の知見と併せて所有者に伝え、保存、活用に向けた協議を進めてまいります。
土地利用の考え方ばかりが先行しているような感じですけれども、区は用途地域や高度地区の変更を予定するとしております。これは周辺住民への住環境にとって大きな影響があるわけですけれども、先ほども述べたように、合理的な理由がないというふうに私たちは考えています。まちづくりは、区民の意見を聞きながら進めるべきです。区の見解を伺います。
冒頭、委員から御説明いただきました旧林愛作邸を含む大規模敷地の土地利用転換が想定されましたことから、旧林愛作邸の現位置での保存、それから周辺環境に配慮しました建築計画を誘導するということを目的に、街づくり条例に基づく街づくり誘導指針を平成二十七年に定めてございます。歴史的資産を生かすことで町の魅力を高めることですとか、緑の保全、創出、広場状の空地、貫通道路の整備など、災害に強い都市基盤を整備して良好な市街地環境の形成を図ることを目指してございます。
また、本年八月に策定しました駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方では、街づくり誘導指針を踏まえながら、旧林愛作邸の現位置での保存のために、本来、建築できる床面積の利用につきまして、都市計画諸制度、いわゆる地区計画の位置づけなどの活用を図りつつ、周辺環境に配慮した建築計画へ誘導することなど、魅力ある町をつくることを土地利用の目標として定めてございます。また、この十月には周辺住民の方への説明会も予定をしてございます。
この基本的な考え方に基づきまして、都市計画諸制度の活用に当たりましては、周辺住宅地への影響を十分に考慮した検討を行いながら、適宜地域の方々との意見交換、説明の場を設け、御意見等を伺いながら、所有者との協議も重ねて、土地利用の基本的な考え方に示しますまちづくりを丁寧に進めてまいります。
この土地利用のために建築制限を緩和するという考え方が、要望を受けてこういうふうになっているということですけれども、本当にそれが必要なのかというのは区は住民にしっかり説明する必要があるかなというふうに思います。そこが重要だというふうに思っていますので、それは説明会などでも取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、適正な利用者負担の導入指針についてです。
区は今議会に、物価高騰、光熱費値上げ等により施設の維持管理費が膨らんでいることを理由に施設使用料の値上げの考え方を示しました。代表質問では、区民活動を進める立場から、使用料の値上げ率を抑えるべきであり、値上げ据え置きなども含め検討することを求めました。
区から、五十平米以下の会議室などは値上げ率を抑え、高齢者や障害者、子どもの施設利用について一定の配慮を検討している。十一月に区民意見募集を予定しており、広く意見を伺うとの答弁がありました。引き続き、使用料の値上げ率を抑え、値上げ据え置きも含め、検討することを強く求めるものです。
併せて、適正な利用者負担の導入指針について見直しをすることを今回求めたいと思います。平成二十二年十二月に策定された適正な利用者負担の導入指針は、全ての利用者負担について、利用する者と利用しない者との公平性を保つことやサービスの公平性の度合い等を踏まえた上で利用者負担の適正化を図ることを目的とすると記載されたもので、応能性よりも応益性に着目し、負担能力の乏しい住民は、必要性の有無にかかわらず、事実上、公共サービスの利用を諦めるようなことが起こりかねない、そういう考え方です。
現区政では、新実施計画後期以降、行政経営改革は、単に財政基盤の確立のため、区民サービスカットと負担増を目的に行うのではなく、むしろ区民サービスの向上と負担軽減を目指して行政手法の改善を行うことに趣旨を置いてきました。適正な利用者負担の導入指針が現状合わないものとなっています。この際、適正な利用者負担の導入指針の見直しを求めます。見解を伺います。
委員お話しの指針でございますが、平成二十二年十二月に策定した適正な利用者負担の導入指針であり、その中で、施設やサービスを利用する者と利用しない者の公平性を保つことが目的の一つとして記載されております。
また、この指針では、施設やサービスについて、選択的か、必需的か、公益性が高いか、私益性が高いかという二つの観点から四つの類型を想定し、各類型ごとに利用者負担割合の目安を定めており、この考え方は現在も用いております。
今回は指針の考え方に加え、管理運営経費の増減に力点を置いて改定を進めております。この指針は、策定時からこの間改定を行っていないことから、今後、今回の改定方法を参考としながら標準的な改定方法について記載するなど見直しを図りたいと考えております。
適正な利用者負担の導入指針の中に記載されている利用する者と利用しない者との公平性の考え方、これは公共の考え方とは相入れないものであり、削除することを求めておきます。
次に、アスベスト対策についてです。
アスベストは非常に有害な物質であり、解体時に空気中に飛散すると健康被害を起こす可能性があり、吸い込むと肺に深刻な影響を与えます。肺がん、中皮腫、アスベスト肺などの病気を引き起こすリスクがあります。解体作業中にアスベストが飛散しないよう適切な対策を取ることが法律で義務づけられました。
アスベストが使われている建物の解体がこの十年がピークだと言われています。工事を行う事業者や工事を行う周辺の住民の健康を守るためにも、アスベストの含有状況の事前調査、飛散防止措置、作業員の保護具着用、周囲の環境保護などが重要です。
区は今年度より建設業人材育成支援事業を拡充して、新たにアスベスト含有建材調査資格者を対象に加え、受講費の一部を補助しています。しかし、事業者の方から、アスベスト含有建材調査資格者に関する補助について、個人事業主や一人親方が対象になっていないので改善してほしいとの要望をいただきました。所管に確認したところ、実際には対象になっているということが分かりました。区のホームページやチラシなどを見ますと、対象者として従業員との記載があります。これを見て、従業員とは違うから対象とはならないというふうに思われたのだと思います。相談者のほかにも、補助金を受けられないと申請を断念した方が一定おられるのではないかと考えます。
ホームページやパンフレットなど、個人事業主や一人親方も対象になるということが分かるよう直ちに表現を変えて周知をしていただきたいと思います。見解を伺います。
建築物の解体等の工事に当たりましては、建築物等の規模や用途、建築時期を問わず、工事の全ての建材についてアスベストの含有の有無を事前に調査するということになっておりまして、昨年十月以降、有資格者による調査の実施が義務づけられているところです。
そのため、区では、今年度より建設業人材育成支援事業を拡充し、新たにアスベスト含有建材調査資格者を対象に加えまして資格取得費用の一部を補助することで事業者の負担軽減を図っております。この事業は個人事業主の方についても活用いただける事業となっておりますので、そのことをホームページやチラシにしっかりと明記し、改めて団体等を通じて周知するとともに、今後、事業者向けメールマガジンの活用など事業のさらなる周知を図ってまいります。
委員 本当にそういったことは重要ですので、早速取り組んでいただきたいというふうに思います。
また、事業者の方からなんですが、施主がアスベスト事前調査の義務化について知らなかったので、費用負担があることも納得していただけない、そういう方が多くて困っているというふうに伺いました。区民に対してアスベストに関する情報周知を進めていただく必要があるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
アスベスト含有建材の有無の事前調査についてなんですけれども、これまで実際に義務が課せられている事業者向けの周知を中心に行ってきました。おっしゃるように、一般区民の施工主の方にも御理解いただけるような周知が必要だと考えておりまして、今年度は「区のおしらせ」に掲載する予定なんですけれども、今後それを定期的に行うとともに、区のホームページの記載も事業者向けのほかに区民向けの記載もしていく、このような改善をしていくとともに、また、様々な機会を捉えて義務化されているという事実が区民の方に理解されるような周知の方法を工夫してまいります。
委員 この間、他会派からも要望が上がっていまして、アスベストの除去費用への助成ですね。今回は求めませんけれども、これも本当に必要じゃないかというふうに思いますので、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。
早いですけれども、以上で日本共産党の質疑を終わります。