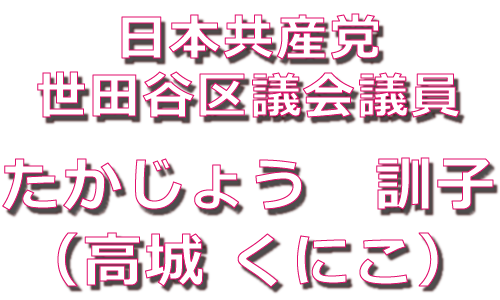

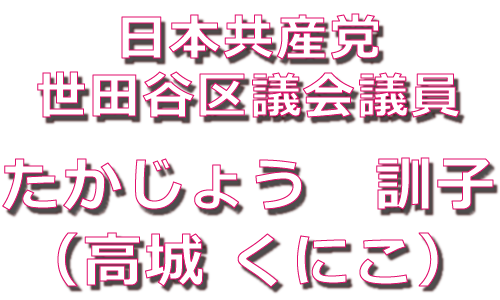

2024/09/17
日本共産党世田谷区議団を代表し、質問します。
裏金事件などで内閣支持率が急落し、世論に追い詰められて退陣を表明した岸田文雄首相自民党総裁の後任を決める自民党総裁選が九月十二日に告示され、九人が立候補を届け出ました。
総裁選候補が改革を言いながら、裏金事件の真相究明に誰も言及せず、非核三原則の見直し、憲法九条への自衛隊明記など、軍事大国化の促進や解雇規制の緩和、残業時間の規制緩和など、貧困と格差を拡大させた新自由主義のさらなる推進の声が上がるなど、酷政、悪政のさらなる競い合いとなっています。
早期衆院解散総選挙との報道がされていますが、衆参両院の予算委員会で裏金事件や政策も含め、何をやるのか、しっかりと議論した上で国民に信を問うべきです。
総裁選で誰が選ばれるにせよ、政治の抜本的転換が必要です。自民党政治をもとから変えるために、日本共産党は全力を尽くします。
それでは質問に入ります。
まず、災害対策についてです。
震災時は在宅避難が基本と言われる中、食料や日用品、薬など支援物資が届く保証があるのかと、区民からの不安の声が聞かれます。特に歩くことが困難な高齢者や障害者などにとって切実な問題です。
今般、物資配送計画策定の検討状況が報告され、今後、検討中の世田谷区地域防災計画に盛り込まれる予定です。
備蓄倉庫について伺います。
災害時に支援物資を確実に指定避難所などに配送するためには、都と区が備蓄する区民の三日分の備蓄品を区内で保管するようにすることが必要です。今後、整備予定の上用賀公園における備蓄品保管スペースは約二千平米です。令和十三年度の竣工までの備えはどうするのでしょうか。また、上用賀公園で備蓄倉庫が完成したとしても、それで十分なのでしょうか、不足分をどこにどのように保管していくのかを伺います。
緊急輸送道路沿道建物の耐震化についてです。
指定避難所に確実に支援物資を届けるには、輸送道路の確保が必要となります。現在、区では、建物の倒壊などにより道路が寸断されて支援物資が届けられないということがないよう、緊急輸送道路沿道の耐震化を進めています。
高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と、都が指定する防災拠点を相互に連絡する道路の中で、特に沿道建物の耐震化を図る必要があると認める道路を特定緊急輸送道路としています。
区は、今般の地区防災計画(素案)において、令和十三年度完成予定の上用賀公園拡張事業で整備予定の体育館の施設内の備蓄倉庫を地域内輸送拠点として活用するとしています。
しかし、この大事な地域内輸送拠点が接する世田谷通りは、特定緊急輸送道路に指定されていません。現状、特定緊急輸送道路沿道の建物の耐震化率は八五%ですが、上用賀公園の前の世田谷通りについては耐震化がどれだけ進められているかさえも分かりません。
上用賀公園の地域内輸送拠点の機能を果たすため、上用賀公園に接する世田谷通り沿道の建物について耐震化の強化が必要です。今年度から改定作業を進めている耐震改修促進計画への反映を求めます。同時に無電柱化のスピードアップを求めます。見解を伺います。
次に、令和七年度予算編成に向けた区の姿勢について伺います。
令和五年度決算での執行残は約二百二十六億六千三百万円、翌年繰越財源を差し引いた実質収支は約百十一億円となりました。年度末における基金残高は約一千四百七十億円で、特別区債残高四百八十一億円です。引き続き区の財政は健全な状況です。今後さらに暮らしのために使う財源はあります。
区は依命通達において、物価上昇に比して実質賃金は複数年にわたってマイナスで推移するなど、賃金上昇を超える物価高騰があるとの見解を示しています。今年度より、生活保護世帯からの大学や専門学校への進学を応援するため、返済不要の奨学金制度を創設し、今般、子育て世帯への住宅支援も行うことが示されました。
生活困窮は、低所得者、高齢者、生活保護世帯において特に深刻です。一日の食事を三回でなく二回にしている、一食を二回に分けて取るようにしている、コロナが五類になり、治療薬が高く手が届かないなどの声も聞かれます。
子ども食堂を運営している方からは、利用希望がキャパを超えてしまい、切実な方を優先して運営するようになった。中高生で会食は卒業したけれど、支援が引き続き必要な方に弁当を出している。家では果物は買えないので、会食で出る果物がありがたいとの声があり、毎回果物を準備している。利用者の三十七人中十五人が、ひとり親で、その状況が深刻なため、ひとり親家庭を対象としたフードパントリー支援も一年前から始めた。夏休み中、学童に持っていく弁当を作る食材がない。分けてもらえないかと連絡を受けて、急遽社協から食材を調達し届けた。貧困の質がコロナ前と明らかに違うと伺っています。
食べるにも困る状況など、これだけ顕在化している貧困に対し、身近な自治体として、豊かな財政基盤を活用し、必要な支援を行うべきと考えます。
区民の暮らし・福祉を守ること、区民生活に欠かすことのできない区内事業者の経営を支えることがより一層求められます。今後の補正予算、来年度予算編成に向けた区長の姿勢について伺います。
生活保護世帯への支援についてです。
昨年、生活保護基準の見直しが行われました。定額減税に伴う措置も行われましたが、物価高騰はこれを上回るものであり、十分とは言えません。電気代の支払いが怖くてエアコンをつけることができないなどの声が寄せられています。生活保護世帯への夏季加算実施を求めます。見解を伺います。
就学援助の拡充についてです。
報道によると、葛飾区は、物価高騰が続く中、子育て世帯の経済的負担を軽減するとして、九月五日、区立中学校の修学旅行費を来年度から無償化する方針を発表しました。二十三区初の取組です。修学旅行では、中学三年生が二泊三日、京都、奈良で、従来は交通費や宿泊費で一人当たり七万円程度でしたが、来年度は物価高騰などで八万円程度になる見込みと報道されています。対象人数は約二千九百人で、約二億三千二百万円とのこと。
世田谷区の場合、区の試算では、例えば現在の就学援助の支給範囲は生活保護基準の一・四倍ですが、これを一・五倍へと引き上げた場合、四千万円の増額で実現可能です。
中学校三年生の修学旅行を、就学援助のかつての給食無償化ラインの世帯まで無償にした場合、対象は四百人増で、二千七百万円の増額で実現可能です。
就学援助は生活保護基準を活用した制度ですが、生活保護基準の物価高騰への対応が十分とは言えません。子どもの貧困が深刻化する中、必要な学用品が買えない、家庭の事情で修学旅行に行けないということがないよう、就学援助の拡充を求めます。見解を伺います。
職員の働き方についてです。
区は、職員の働き方を改善させるためとして、新たな行政経営への移行実現プランでアウトソーシングの推進方針を示しました。公務員の成り手が減少し、当区でも慢性的な人手不足となっています。現場が疲弊し、質の担保も叫ばれる中、委託や民営化、派遣が進められています。従来の行革から抜け出せず、負のスパイラルに陥っているのではないでしょうか。
今年七月三日、博報堂生活総合研究所が「若者調査」三十年変化の結果を発表しました。今一番欲しいものについて、一位がお金、二位は時間、三位が自由、四位が安定した生活という結果でした。役所が若者に選ばれる職場になるために必要なのは、役所自身がディーセントワーク、つまり権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的保護が与えられる生産的な仕事を目指すことです。初任給を引き上げたり、残業をなくしたり、裁量のある仕事ができる、そんな働き方を実現し、若者にとって魅力ある職場へと変えていくことが必要ではないでしょうか。
具体には、現業職の退職不補充方針の撤回、必要な人員増員計画を明らかにすること、公務員ヘルパーの欠員解消、清掃職員の配置基準と計画的増員、学校用務員の委託の見直し、非正規から正規への切替えを進めるべきと考えます。
公共サービスの提供は、区職員による直営を基本とするべきです。その実現のため、積極的な考えを区内外に向け、区長に発信していただきたいというふうに思っております。区長の見解を伺います。
公共施設の使用料見直しについてです。
区は、物価高騰、光熱費値上げ等により施設の維持管理費が膨らんでいることを理由に、使用料の値上げの考えを示しました。
前回、平成三十年、二〇一八年の見直しは、全ての利用者負担について、利用する者と利用しない者との公平性を保つことや、サービスの公共性の度合い等を踏まえた上で、利用者負担の適正化を図ることを目的とすると記載された、適正な利用者負担の導入指針に基づいたものでした。
そもそも、集会施設にしろ、子育て関連の施設にしろ、公共施設の維持管理は、地方自治法第一条の二に書かれた住民の福祉の増進を目的に掲げる自治体が、一般会計の主要な歳入である税によって賄うべきものであり、無料にするべきです。
しかしながら、この間、光熱費等の維持管理費の一部が利用者負担となり、使用料が引き上げられてきた経緯があります。今回の見直しは、基本計画、地域行政推進条例、今回の子ども条例一部改正(素案)で述べられている低所得者への配慮や住民自治の発展、子どもの参加する権利などの視点が盛り込まれました。一定配慮あるものになっていると考えます。あわせて、利用する者と、しない者との分断を招く、適正な利用者負担の導入指針を廃止することを強く求めるものです。
区民が学び、集う場所の確保は重要であり、使用料の値上げがこれを阻害するものになってはならないと考えます。区民活動を進める立場から、使用料の値上げ率を抑えるべきです。地区会館や集会所について、値上げ据置きなども含め検討することを求めます。
また、けやきネット利用者をはじめ、施設利用団体に対し考え方を知らせ、意見を聴く必要があります。見解を伺います。
介護職員への処遇改善策についてです。
今回の補正予算に、介護を必要とする方が継続的にサービスを受けられるよう、区内の介護事業者への経営支援が盛り込まれました。しかし、さきの福祉保健常任委員会において出された介護職員の処遇改善を求める陳情が全会一致で趣旨採択されたことを考えれば、一時的なものではない継続的な支援が求められます。
介護職の賃金は、国と東京都の助成を合わせても依然全産業平均収入から月六万円も低く、抜本的な改善には至っていません。
今後さらに高まる介護ニーズに応えていくために、来年度予算において継続的な処遇改善策を講じることを求めます。
さらに、介護職員の賃金を少なくとも全産業平均並みに引き上げるために、国に対し介護報酬の引上げと、介護保険の保険料と利用料を上げないための国庫負担割合の引上げを併せて国に強く求めていただきたい。見解を伺います。
次に、世田谷区子ども条例の一部改正(素案)についてです。
今議会に世田谷区子ども条例の一部改正(素案)が示されました。一九九四年、国は、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重の四つの権利が定められている子ども権利条約に批准しました。しかし、批准して三十年たっても、日本社会では、子どもが権利の主体として尊重されていません。こうした中で、世田谷区が子どもの権利を明記する条例を制定することは意義があります。
虐待や貧困、ヤングケアラーなど、家庭の中で苦しむ子どもたちや保護者をさらに追い詰め、一層孤立させている現状や、国連から繰り返し勧告を受けているように、過度な競争・管理教育、いじめ、不登校など、学校教育における権利侵害があります。
このたびの子どもの権利条例は、ここに向き合った内容となっており、評価いたします。
これに加え、以下の点について条例に盛り込むことを求めます。
1、今後、DXの推進により、生まれたときから子どもの個人情報が集積され、本人の不利益な情報がデジタルタトゥー、ネット上に消せずに残る負の情報として将来にわたり影響を及ぼしかねない状況が懸念されます。政府が、個人情報を民間企業のもうけの種として利活用する政策を推進している下、プライバシー権の侵害やプロファイリング、スコアリング、点数化などによる権利侵害などです。こうした権利侵害から子どもを守る観点も加えること。
2、幼児期、小学生からの包括的性教育、体を知り、セルフケアをし、何かあったら誰かに相談するといった、自分の性を通して自分で選び、決めていく力を育み、科学と人権の視点に基づいた体の権利教育を進める必要があります。性暴力から子どもを守るためにも、子どもの体の権利を守る観点を加えること。
また、既に教育振興基本計画は今年度からスタートしています。教育現場において、今後、条例をどう位置づけ、反映させていくのか伺います。
次に、千歳烏山駅周辺まちづくりについて伺います。
駅周辺のまちづくりについては、これまで駅周辺の商店街、また、駅の南側で再開発の検討を進めている再開発準備組合などを中心に話し合われてきました。
九月三日の都市整備常任委員会において、駅周辺まちづくりについての報告があり、今般、地域の住民やまちづくりに関する活動団体、京王電鉄、専門家などを含めた情報共有・意見交換の場が設けられるとのこと、これを評価いたします。今後、こうした議論の中でまちづくりが進められることを望むものです。
駅の南側の地区では、再開発準備組合が結成され、検討が進められており、第一種市街地再開発の手法で進められると伺っています。
区では、これまで幾つかの再開発の事例があり、そのたびに多額の税金が投入されてきました。例えば、規模が違いますが、二子玉川の再開発では、総事業費約一千四百三十八億円に対し、補助金の総額が百五十六億円、約一割が国、都、区の税金で賄われてきました。
このように再開発は多額の税金が投入される事業であることから、区民への情報公開を積極的に行い、区民の声を聴いていく必要があります。区の負担、今後の取組について伺います。
最後に、北烏山地区会館の代替施設についてです。
北烏山地区会館を用途転換し、寺町通り区民集会所への統廃合方針が決定しました。そのために三十人規模の集会室が地域からなくなってしまいます。地域の方々は、代替施設の確保を求める署名に取り組んでおり、現在二百七十筆集まっていると伺っています。
これまで区は、代替施設を確保すると答弁してきました。今どうなっているでしょうか。早期に、そして確実に対応していただきたい。見解を伺います。
以上で壇上からの質問を終わります。
たかじょう議員にお答えをいたします。
今後の補正予算、来年度予算編成に向けた区長の姿勢ということで御質問いただきました。
この間、二か月連続で実質賃金がプラスに転じた一方で、物価高の影響がまだ続いており、依然としてこの傾向が収まらず、区民生活は依然として厳しい状況が続いているものと認識しております。
来年度の区の財政見通しとしては、特別区税の一定の増を見込んでいるものの、物価高騰等を反映すれば、歳出は全体的に増加することが想定され、また、ふるさと納税の流出動向を見据えると、決してゆとりのある状態ではありません。
このような中で、持続可能な未来を確保し、あらゆる世代が安心して住み続けられる世田谷をともにつくるという区の目指すべき方向性の実現に向けて、財源や人員などの経営資源を有効に活用することを念頭に置きまして、今後、来年度の予算編成に取り組んでまいります。
また、今般の一般会計第二次補正予算案において、区独自の施策として、高齢者、障害者施設等への安定経営支援給付金を盛り込むなど、区民生活に欠かせない福祉サービスが滞ることのないよう、国や都に先んじて対応をしていきます。
今後も区民の生の声が聞ける自治体の特性を生かし、適切に補正予算での対応も行ってまいります。
次に、公共サービスの在り方、区職員による取組を基本とせよということでございます。
今後ますます高まっていく行政需要に対しまして、職員の確保が困難になる状況が生まれつつあることを見据えると、内部定型事務を中心に、DX推進やアウトソーシングによる効率化を進めながら、一方で職員の力を福祉の相談支援、あるいはまちづくりの合意形成のほか、企画立案や審査、許認可など、判断を要する業務に振り向けていくことが不可欠であるため、私は新たな行政経営への移行実現プランを策定をいたしました。
なお、アウトソーシングした業務の最終的な責任が区にあることは言うまでもありません。このため、区民サービスの質の確保や、委託業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保など、その運用を確保するよう指示しているところであります。
区の業務も年々拡大をしておりまして、必要に応じた住民サービスを支える組織強化と人員の手当てにもきちんと取り組んでまいります。
こうした状況から、必要な職場に人員を適切に配置していくことができるよう、これまでの職員数の上限を六千人まで引き上げる職員定数条例の改正を提案し、議決をいただいたところでございます。
区全体の公共資源を的確に把握し、人材を効果的に配置し、山積する区政課題に的確に対応することで、公務労働に高い志を持つことはもとより、やる気に満ちあふれている若い世代に就職先、仕事先として選択されるよう、働きやすく魅力ある世田谷区を発信し、この実現に全庁挙げて取り組んでまいります。
以上です。
私から、介護職員の処遇改善策等について御答弁いたします。
区は、この間の国の介護報酬の一部マイナス改定や、介護事業所の過去最多の倒産件数など、高齢者・障害者施設の危機的な経営環境を踏まえ、区民に必要な福祉サービスの事業継続を支えるため、緊急対策としての給付金事業を補正予算案に計上したところです。引き続き国や都の動向や社会経済状況を注視しつつ、介護人材確保のための処遇改善や、区民に必要な福祉サービスの事業継続という観点から、必要な支援策の実施について判断をしてまいります。
本来、介護人材確保のための処遇改善や事業所の安定経営については、国の責任において必要な介護報酬改定や国庫負担割合の見直しを行うべきと考えています。機会を捉えて国に要望を伝えてまいります。
以上です。
私からは、上用賀公園前の世田谷通り沿道の建築物について耐震化の強化を進めよ、また、無電柱化のスピードアップについて御答弁申し上げます。
現在、修正作業を進めております世田谷区地域防災計画において、上用賀公園拡張事業で計画中の体育館は、物資の地域内輸送拠点としての活用も想定しており、体育館への輸送経路ともなる都道の世田谷通りは、一般緊急輸送道路となっております。
区では、特定緊急輸送道路、一般緊急輸送道路や沿道耐震化道路について、震災直後の避難、輸送経路を確保するため、一定の高さを有する沿道建築物に、他の非木造建築物よりも手厚い耐震化の支援、助成をそれぞれ行っております。
しかし、一般緊急輸送道路沿道建築物は、特定緊急輸送道路沿道建築物に比べて、近年、助成制度の活用がなされていない状況であり、助成内容に差があることも耐震化の取組が進まない要因の一つと考えられます。
区としましては、啓発の取組を続けるとともに、今年度より検討を開始しました世田谷区耐震改修促進計画の改定作業の中で、必要となる助成内容について調査研究を進め、各沿道建築物のさらなる耐震化の促進に取り組んでまいります。
また、緊急輸送道路の機能確保には、沿道建築物の耐震化に加え無電柱化も有効であり、東京都の無電柱化に関する計画に位置づけのある路線の早期着手など、東京都に対しまして様々な機会を通じ働きかけを行ってまいります。
以上です。
私からは、備蓄物資の保管スペースの確保について御答弁いたします。
区では、物資供給体制の整備を地域防災計画修正の重点検討項目として位置づけ、物資配送計画の策定や備蓄物資の保管スペースの確保等について検討を進めております。
指定避難所の発災後三日分の食料等につきましては、区が一日分、都が二日分を用意することとなっておりますが、現在、都が用意する食料等の多くは、発災後に羽田クロノゲートにおいて都から受領し、各指定避難所に配送することになっております。
このため、発災後、物資を迅速に指定避難所に配送できるよう、令和十三年以降に竣工予定の上用賀公園内の体育館には、約二千平米の大規模備蓄倉庫を整備し、都の用意する食料等を備蓄する計画としております。
一方で、生活必需品まで備蓄するためには、さらなる保管スペースの確保が必要です。今後、区施設等を有効活用して倉庫の拡充を検討するなど、計画している大規模備蓄倉庫整備までの約二千平米分のスペースを含めて、早期に物資の保管スペースが確保できるよう取り組んでまいります。
私からは以上です。
私からは、生活保護夏季加算について御答弁いたします。
生活保護基準については、国が五年に一度、生活保護を利用していない低所得世帯の消費実態とのバランスについて検証を行っています。令和五年十月に見直した生活扶助費の基準については、仮に検証結果をそのまま反映すると、世帯構成によっては金額が下がる場合もあるため、令和六年度までは、これまでの生活扶助費の基準から下がる世帯がないようにする臨時的・特例的な措置が行われています。
区としても、生活保護世帯の実態を踏まえ、都市部のヒートアイランド現象、昨今の電力料金値上げなどから、東京都を通じ夏季加算の新設を国に要望しています。引き続き、経済的理由でやむを得ずエアコンの利用を控えている方などに対して、熱中症対策の重要性を丁寧に説明しつつ、適宜家計相談に応じながら、お休み処の活用など、猛暑の中でも安心して安全に過ごすことができるよう支援をしてまいります。
私からは以上です。
私からは、二点について御答弁いたします。
まず、就学援助の拡充についてでございます。
教育委員会では、物価の高止まりなど、昨今の社会経済情勢を鑑み、区立小中学校の給食費無償化をはじめ、教育に係る保護者の経済的負担の軽減に取り組んでいるところでございます。就学援助に関しましては、認定基準の設定の際に参照している生活保護基準が、平成三十年十月に段階的に引き下げられた見直しの際も、支給範囲の縮小を行っておらず、さらに、社会経済情勢に鑑み、令和元年度には認定基準を引き上げ、支給範囲を拡充いたしました。また、該当者が漏れなく受給できるよう、入学時の全員周知にも取り組むなど、丁寧な対応を心がけてまいりました。今後も、社会経済情勢が学齢期のお子さんのいる家庭に及ぼす影響を鑑みながら必要な支援を行ってまいります。
次に、教育現場において今後、子ども条例をどう位置づけ、反映させていくのかとの御質問でございます。
子どもの意見を尊重した施策を推進するためには、子どもの権利条約や、こども基本法における、子どもを個人として尊重する、子どもの意見を尊重するなどの基本理念を踏まえておくことが必要でございます。
その上で、子ども自身が意見を率直に言える環境を整え、子ども自身が関わる社会や制度に参画し、表明した意見や考えが反映できる仕組みを整えていくことが大切であると考えております。
このことは、令和六年三月に策定いたしました教育振興基本計画に盛り込んでおり、子どもを主体とした教育を本計画の最も大切な視点としていくとともに、子どもの学びや成長に関わる全ての関係者と共通理解を深めることを重点的な取組としております。
現在、子ども条例の改正が検討されておりますが、その検討結果を踏まえた教育が推進されるよう各学校へ働きかけていくとともに、現在の教育振興基本計画の次期改定時のタイミングでは、改めてそのときの状況や考え方等も踏まえ、子どもの意見が反映される、子どもを主体とした教育の推進について検討いたします。
以上でございます。
私からは、公共施設の利用料見直しについてお答えいたします。
区では現在、公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景とした使用料等の引上げ改定の検討を進めております。議員御指摘のとおり、地区会館や区民集会所等はコミュニティーの創出を目的としており、使用料等の値上げによってこの目的が阻害される結果となることは望ましくないものと考えております。
地区会館や区民集会所等は公益性が高く、もともと低廉な料金が設定されており、区民集会施設にあっては、例えば五十平米以下の会議室などは、改定額が一時間当たり数十円単位、会議室の面積が大きくなれば数百円程度の改定を想定しております。
加えて、改定幅が大きくなり過ぎないよう、原則として改定幅の上限を三割と考えているほか、高齢者や障害者、さらには子どもの施設利用についても一定の配慮を検討しております。
改定額の決定に当たっては、十一月に区民意見募集を予定しており、施設を利用する方、しない方双方から広く御意見を伺ってまいります。
私からは以上です。
私からは、子ども条例の一部改正(素案)に関し、個人情報保護の観点や、子どもの体の権利を守る観点も加えるべきとの御質問についてお答えいたします。
子ども条例の一部改正(素案)は、子どもの権利が保障されるまちを文化として築いていくことを目指しています。今回の改正においては、第二章、子どもの権利において、子どもの権利条約が原則とする四つの権利を引用し規定するとともに、小学生、中学生アンケートや児童館や青少年交流センターで実施しました子ども・青少年会議などで、子どもたちから聴いた意見などを踏まえ、中高生世代の子どもたちが検討を行い、子どもたちが特に重要と考えた権利を明示する形で記載しています。
日本国憲法や子どもの権利条約等が保障する子どもの権利を全て条例に規定するというものではなく、また、条例に規定した権利のみが保障されるということでもございません。御指摘の子どもの個人情報が保護され、子どもの体の権利を守ることについては、子どもが豊かに育つために保障されるべき大変重要な権利であると認識しております。
法令等で保障されているこれらの権利を条例に規定することについては、子どもの意見を踏まえた議論を重ね、検討を進めてまいります。
以上です。
私からは、二点御答弁いたします。
まず、千歳烏山駅周辺のまちづくりについて、再開発には多額の税金が使われていくことになると思われるが、区の負担についてです。
千歳烏山駅周辺では、京王線連立事業や駅前広場などの都市計画事業を契機に、まちづくりを進めており、駅前広場を含む南側地区では、区も活動を支援し、地権者により再開発事業の検討が進められ、令和四年十二月に再開発準備組合が設立されました。その後、施設計画の検討など、令和七年度の都市計画決定を目指した取組が進められております。
再開発事業に係る事業費等の検討は、再開発準備組合により順次進められてまいりますが、再開発事業は、都市基盤整備など都市機能の更新を図ることを目的とした都市計画事業であることから、補助金の対象となります。取扱いは区の要綱に基づきますが、区も一定の負担をすることが見込まれます。
区といたしましては、再開発事業の取組について、引き続き駅周辺全体のまちづくりにも寄与するよう関与等をしながら、取組の進捗に応じて、国や東京都の補助金等も活用して対応するなど、主要な地域生活拠点として、さらに魅力的で暮らしやすい町を目指し、まちづくりを推進してまいります。
次に、北烏山地区会館に代わる施設の確保についてです。
北烏山地区会館については、障害者グループホームへ転用する方針を定め、近くの寺町通り区民集会所の二つの会議室をオンラインでつなぐシステムを導入いたしましたが、区民の方からは近隣に一定の広さの施設が必要であるとの要望が強く寄せられております。
近隣では、福祉施設の地域交流のためのスペースについて、コロナ禍以前には、近隣の方の利用も可能でしたが、現在でも、感染症への懸念から利用が難しいなどの状況にあります。
烏山地区では、様々な形でまちづくりの計画が進められているところであり、これらの進展の機会を捉えて、地区の方々が集えるスペースの確保を要望するなど、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
ありがとうございます。それでは、暮らしの問題ですけれども、本当に区の財政状況というのは健全です。今、子どもの貧困状況なんか切実だというお話をしましたけれども、ぜひ来年度予算、それからその前の補正予算などで、しっかりと支援を進めていただきたいということを要望します。続きは決算特別委員会で議論したいと思います。
以上で終わります。